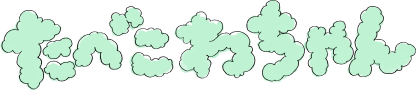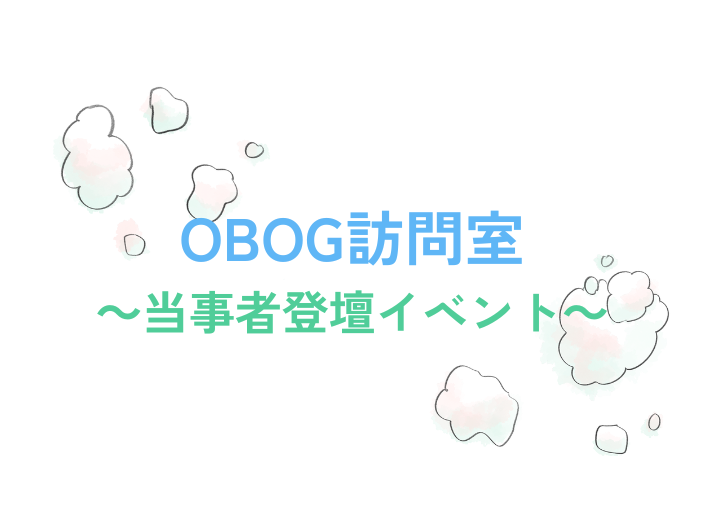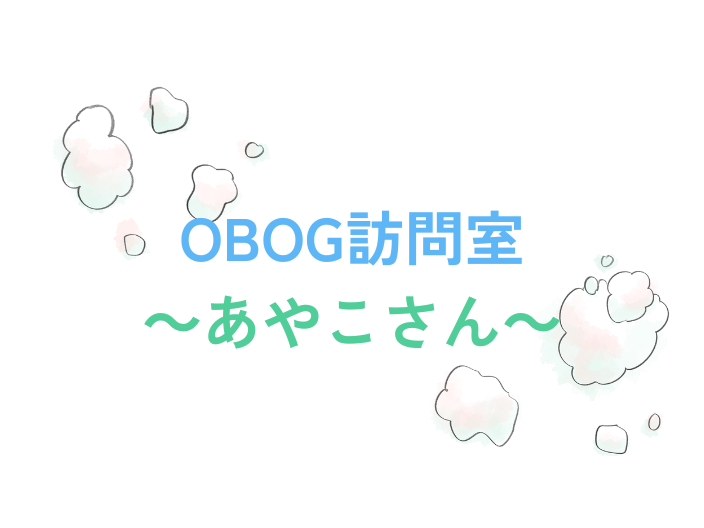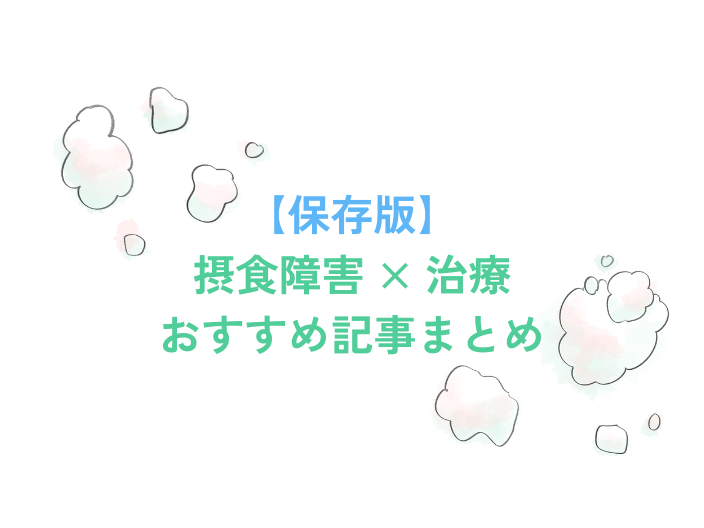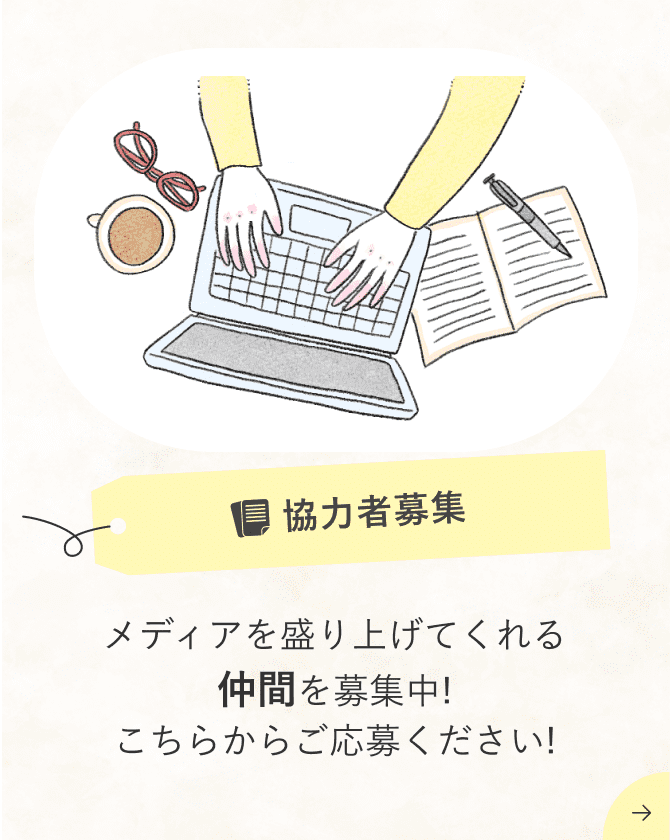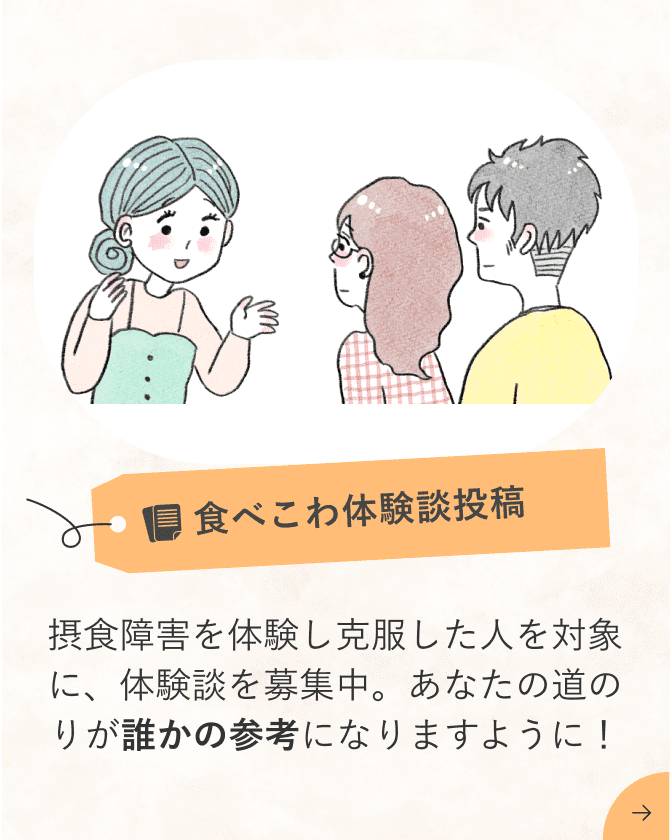中学で始まった「優等生」という生き方
—— 症状が始まったきっかけを聞かせてください
小学校の頃は比較的自由に過ごしていたのですが、中学に入ってから段々と完璧主義になっていきました。中学校って、小学校とは違って規則が厳しくなるし、思春期も始まって人間関係が複雑になる年齢だと思うんです。だからこそ、当時は「自分の居場所を確保しないと」と思っていました。
そんな中でクラスで落ちこぼれにならないための方法が、私にとっては「優等生でいること」でした。常に勉強ができて、スポーツもできて、先生から信頼されて、クラスをまとめる責任感のある人物…そういう存在でいないといけないと思っていたんです。
——「優等生」でいることへのプレッシャーが、食事にも影響したんでしょうか
高校受験のストレスもあったんですが、決定的だったのは環境問題への関心でした。生徒会活動で国際協力機構に行って、世界の飢餓や食料廃棄の現状を学んだんです。すごくショックで、日本では食べ物がこんなに溢れてて捨てられてる…そんなのダメだって、怒りの気持ちが湧きました。
そこから肉を食べない、無駄なく食べるということにこだわるようになりました。学校でも社会でも「優等生」でいないといけないという気持ちから、自分に厳しい食事制限を課していたんです。受験が終わってからは解放感で少しずつ食事が取れるようになりました。でも、その後行った留学先で、また食事制限が始まりました。
異国での孤独と唯一の逃げ場
—— 留学先ではどのような状況だったんでしょうか?
学校にいる時は、言葉もわからず授業にもついていけず、色々なカルチャーショックもありました。クラスの子が大麻を吸ってたり、先生も全然やる気がなかったり、日本で通っていた学校とは何もかも違っていて…。寮で一人になった時くらいしか、心が落ち着く時間がなかったんです。
学校でサンドイッチみたいなものが給食として出ていたんですが、マヨネーズだらけで、とても脂っこかった記憶があります。それを食べると、夜は怖くて何も食べられなくて。誰ともコミュニケーションが取れなくて孤独を感じている中、慣れ親しんだ食事さえ得られなくなったことが本当に辛かったです。日本米をどこで買えば良いのかわからず、スーパーで見つけたタイ米で必死におにぎりを作ろうとしたこともあるんですが、ポロポロしていて全然作れず…泣きましたね。
—— そんな状況で、自分をどう支えていたんですか?
慣れ親しんだ人間関係も食事もなくなった中で、唯一自分らしさを感じられるのが「身体」だったんです。夜、1人になった時に身体を触っていました。今日もちゃんと肋骨に触れるとか、両手で輪っかを作ったところに太ももが入るとか、そういう手で触った自分の感覚に、今までの自分を見出して安心しようとしていたんです。抽象的な言い方になってしまうんですが、自分の輪郭を常に確認してたんだと思います。新しい環境で、自分のアイデンティティが揺らいでいたからこそ、自分の身体を徹底的にコントロールすることで、自分を失わないようにしてたのかな、と。
8月に留学して、冬頃には「このままじゃダメだ」と思うようになりました。食べることがどんどん怖くなって、体調も悪くなって、その頃には自分が拒食症だという自覚もありました。
症状が本当にひどい頃は、日常的なことをするのも難しくなっていました。例えばトイレに行くのも怖かったんです。留学先では公衆トイレが有料のところが多くて、利用する時は人に声をかけて許可をもらう必要があったんですが、当時人と話すこと自体がすごく怖くなっていたので、道端の茂みで用を足そうとしたこともありました。その時に「これは今までの自分と違う、何かがおかしい」と思ったんです。でも「こうするしかない」って信じ込んでいて、理性と行動が全然噛み合わない状態でした。
—— 当時、帰国は考えましたか?
日本に帰ることが唯一の解決策だという感覚は自分の中にもあったんですが、一年前に取った飛行機の時期を早めることはどうしても出来ませんでした。留学した以上は最後まで頑張らないとって思っていたんです。最後の一ヶ月ぐらいは本当に体調が悪くて、医療的なケアも必要な状態だったんですが、「途中で投げ出すなんてできない」と自分を追い込んでいました。
その状況で自分を支えてくれたのが、スケッチブックでした。自分の気持ちを言葉で言い表すことができないから、その代替手段として絵を描いてたんです。日記みたいに、毎日毎日。
自分で自分を抱きしめてる姿や、食べ物がトイレに流れていく様子、箱から抜け出そうとしてる自分などを描いてました。絵を描くことで、自分の状況を客観視できている部分もあったと思います。「今の自分は病気の状態なんだ」って冷静に分析している自分と、でもそこから抜け出せない自分と、両方いたっていう感じですね。絵の中には帰国までの日数のカウントダウンや、自分を鼓舞する言葉も入れ込んでました。
—— 当時を振り返ってどう思いますか?
振り返ってみると、拒食症だった当時でも、もし私が「助けて」と言えていれば、クラスメートたちは助けてくれたと思うんです。今でもその一人とは親友で仲が良いんですが彼女からも「辛いって言わないから、しんどいことに気がつかなかった」って言われて。
私の場合は服装で体型を隠していたので、周りも気づくのが難しかったんだと思います。あの時はとにかく「この人たちはみんな私を助けてくれないんだ」と思って、自分からシャットダウンしていました。一度シャットダウンすると、殻に閉じこもって拒食に走って痩せていって…だからそこから出るのがすごく大変だったんだと思います。
壊れた理想像を貼り直して
—— 回復の中で、ご自身の中で何か変化はありましたか?
回復する中で、自分の「優等生」という理想像が完全に崩れたんです。割れた鏡のように壊れた自分の像を、もう一度貼り直していく作業をしているというか、「こうあるべき自分」ではなくて「ありたい自分」になっていくような感覚でした。その時に、自分の好きなことにフォーカスした選択や生き方をしたいと思ったんです。だからこそ、アートの道にもう一度挑戦しようと決めました。
今度は自分一人で、自分の好きな時に好きな料理が作れるような一人暮らし用のアパートを借りて留学を再度スタートしました。一回目の留学は辛かったけど、症状が落ち着いて自分も成長した今なら、もう一度挑戦できると思ったんです。
—— 二度目の留学はいかがでしたか?
留学先の人たちはみんな、とても優しく迎えてくれました。学校のクラスメートが私の描いてる絵を「すごくいいね」と言ってくれたりする中で、辛い思い出しかなかった場所が、自分にとって安全な環境に変わりました。
最初の頃はやっぱり不安は多かったです。でも大学に進学して、自分の絵や自分が生み出すものを評価されることで気持ちも変わっていきました。制服の着方や振る舞い、成績など、誰かが決めた優等生の像に自分を合わせることで存在価値を見出すのではなく、自分が好きでやりたいことに集中した結果を通じて周りと絆を築いていくことが大事なんだって。そういう風に考え方が変わったんです。
体験が現在の創作の原動力に
—— 現在の活動について教えてください
拒食症の経験は本当に大事な意味を持ってます。この経験がなかったら、多分今この仕事をしていないと思います。自分について沢山考える機会でした。
色々な自分が自分の中にあることが大事なんだと気づけたんです。「自分はこうあるべき」ではなくて色々な自分が共存していていいんだと思えるようになりました。そうして、今は一度は拒絶した異なる文化も自分の一部として大切にできるようになっています。
—— 作品のテーマについて聞かせてください
身体についての表現がメインテーマになってます。例えば妊娠したら身体はすごく変わりますよね。そんな風に、身体って常にアメーバみたいに周りと繋がり合いながら変わっていくものだと思うんです。でも実際には、「美しい身体になるために痩せましょう」とか「若くないといけないからアンチエイジングしましょう」とか、そういうメッセージが街中に溢れていて、息苦しさを感じることもあります。
身体はアメーバや植物みたいに生きているから、その変化をある意味楽しむというか、興味深く観察する手段として、私は作品での表現を続けていきたいです。
同じ痛みを抱える人たちへ
—— 同じような状況にある方に、何か伝えたいことはありますか?
「逃げてもいい」ということです。例えば留学している人がいるとしたら、早く帰国してもいいんだよと伝えたいです。留学や海外生活を控えてる人は期待や夢が大きいと思うんですが、コミュニケーションがうまくいかないことで落胆して、自信をなくして、大きな孤独を感じてしまうこともある。そんな時は一人で抱え込まずに、まずは信頼できる人に話してみてほしい。自分を守ることを最優先にしてほしいです。
振り返ってみると、当時の私は周囲がどんなにアドバイスをくれても、意地になって、相談することも日本に帰る決断をすることもできなかったと思うんです。でも実際に環境を変えてみると状況は変わるものなので…なかなか信じるのは難しいかもしれませんが、途中でやめてもいいし、自分に厳しくしすぎなくても大丈夫だということを伝えたいです。
—— 社会に対して知ってほしいことはありますか?
海外で食事が変わるということは、単に「日本の味が恋しい」という話ではありません。私の場合は慣れ親しんだ食べ物がなくなったことで、気持ちが不安定になってしまいました。食べ慣れたものを食べられないのは、思っている以上に心に影響するということに気づいたんです。
だからこそ伝えたいのは、摂食障害の原因が本当に人それぞれだということです。摂食障害はよく「痩せたい願望が原因」と説明されることが多いと思います。もちろん美意識や社会的なプレッシャーも関係していますが、私の場合は環境の変化や慣れ親しんだものを失う不安など、もっと複合的な要因がありました。そういう多様性があることを知ってもらいたいです。
—— 最後に、今の想いを聞かせてください
今は自分の中に色々な自分がいても良いんだと思えるようになりました。完璧な優等生でいなきゃという殻を破り、ありのままの自分を受け入れられるようになったと思います。
でも、あの辛い経験があったからこそ、今の表現活動があるし、同じような悩みを抱えている人の気持ちもわかります。身体も心も、変化していくものだからこそ美しいんだということを、これからも作品を通じて伝えていけたらいいなと思っています。