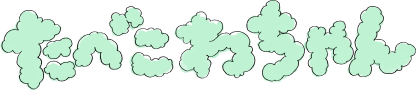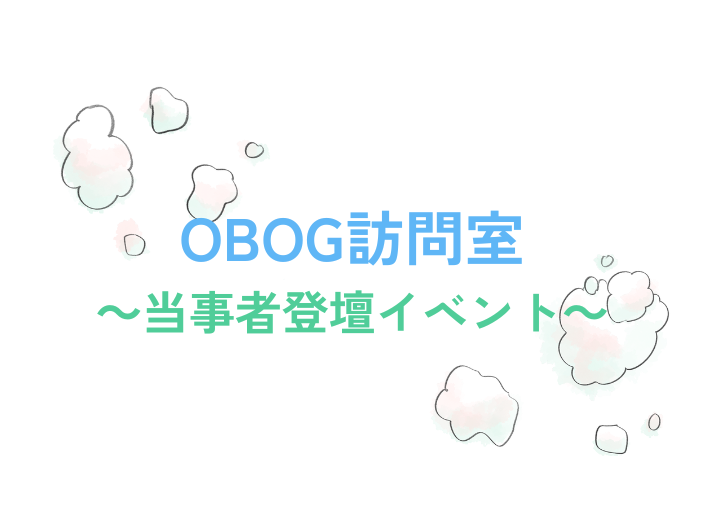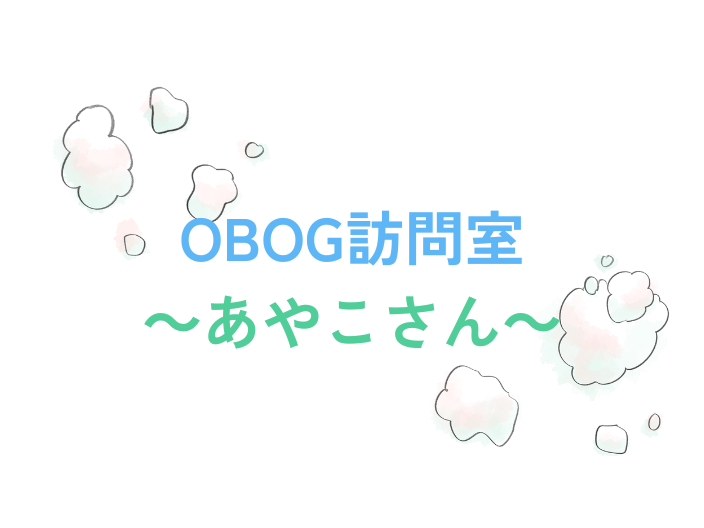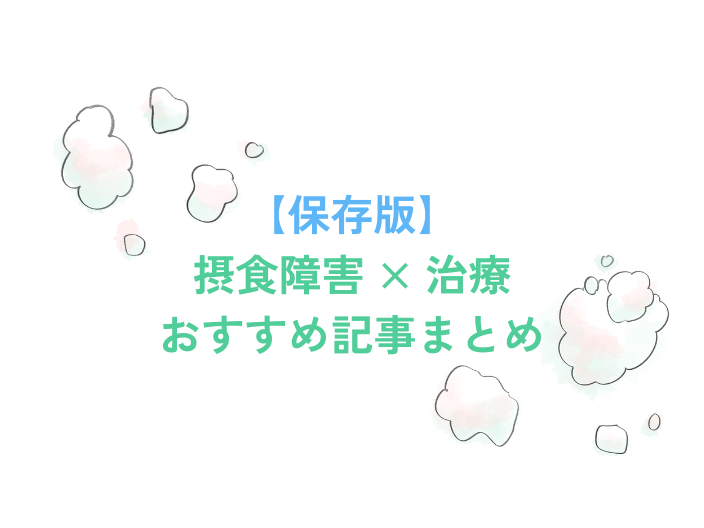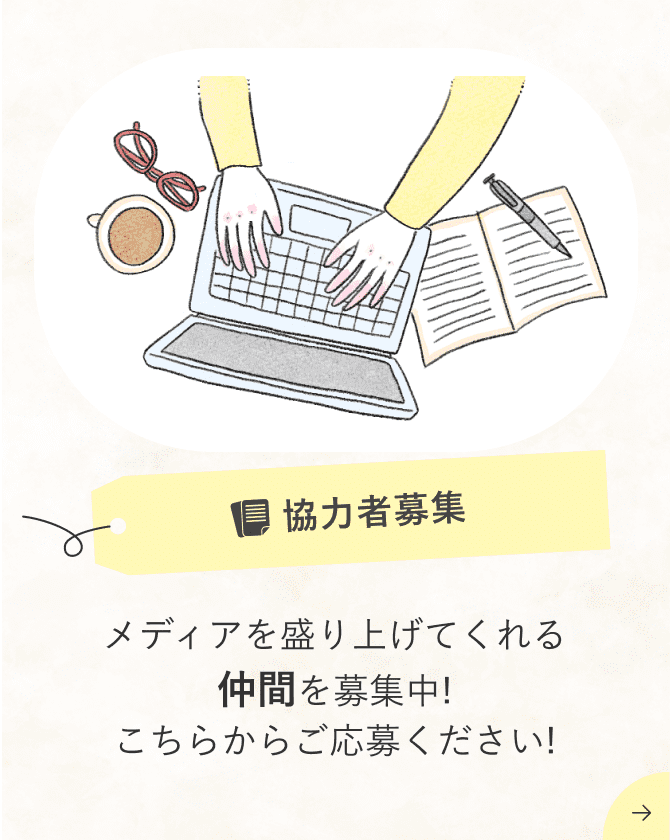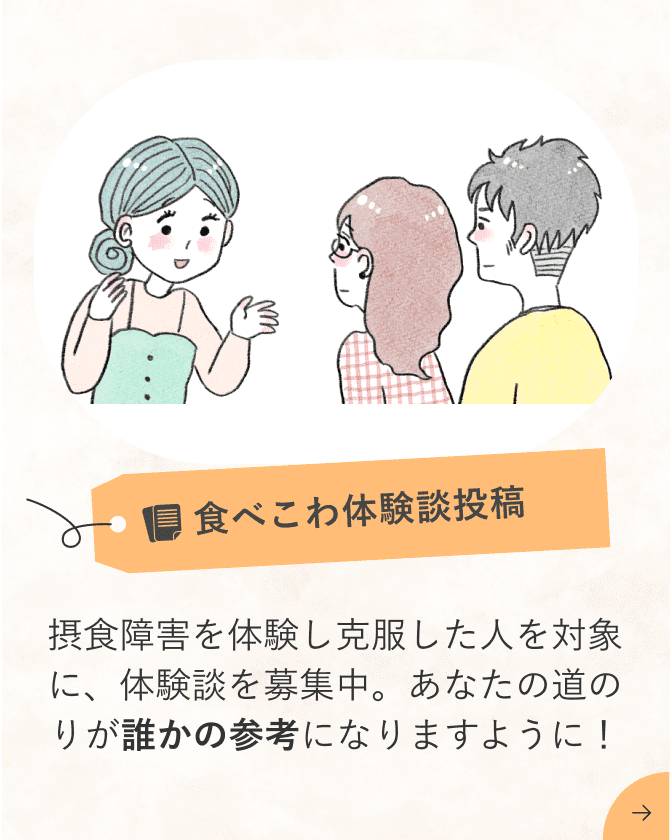「痩せている方がいい」という思いから始まった日々
—— 摂食障害の症状が始まったきっかけを教えてください。
症状が始まったのは、20歳の大学生の時でした。振り返ると、何か特別な出来事があったわけではなく、高校生の頃から少しずつ芽生えていた「痩せている方がいい」という価値観が、徐々に強くなっていった結果だったんだと思います。体型的にはBMIでいうと標準と痩せの間くらいで、今思うとあまり気にするほどのことではなかったんです。でも、周りの細い子を見て「あんな風になりたい」と思うようになっていきました。
高校生の頃から、小さいサイズのお弁当箱に詰めた少量の食事を食べる習慣があって…。周りに「そんなちょっとしか食べないから痩せてるんだよ」と言われると嬉しかったんです。当時は深く考えていなかったんですが、そういう出来事が重なるうちに、自分の中で「少食=良いこと」のように刷り込まれていったのかもしれません。
——食事制限はいつ頃から始められたんですか?
本格的に制限を始めたのは大学に入ってからです。「これ以上は食べちゃいけない」という食事量を自分で決めて、それを守ろうと必死でした。当時は辛いという感情はあまりなくて、食事量をきちんと管理できている自分に満足感を感じていたんです。今思うと、その時から「完璧にできている自分」でいたいという気持ちが強くなっていたのかもしれません。
仕事と学業の両立に追われるうちに過食へ
—— 症状が拒食から過食に変わったのはいつ頃ですか?
大学院修士課程から社会人1年目にかけて徐々に過食へ移行し、社会人3年目頃から状況が悪化していきました。仕事や勉強でストレスがかかると、気がつくと食べてしまうんです。でも、その時は「勉強に集中するためだから」「仕事を頑張るためだから」と自分を納得させていました。
特に27歳から28歳にかけては本当に大変でした。睡眠時間を極限まで削って頑張っても、仕事や勉強が全然終わらなくて。24時間営業のマクドナルドに、気がついたら始発の時間まで居たこともありました。本当はよくないとわかっていても、コンビニで買ったお菓子を食べながら目を覚ましていたんです。
——その頃の生活リズムはどのような状態でしたか?
完全に悪循環に陥っていました。疲れすぎて、食べないと眠気に負けてしまうから、どうしても食べざるを得ない。頭では「寝た方が効率がいい」とわかっているのに、仕事や勉強が遅れるのが怖くて、眠気覚ましに食べ物を口に入れていました。布団に入ると気持ち良くて長時間寝てしまうので、それも怖くて。床に寝転がったり、布団の上に座ったりした状態で仮眠をとるような、そんな生活でした。
当時、「他のことを犠牲にしてでも頑張らないと」という強迫的な思いがあったんです。「このまま食べ続けていたら太ってしまう」という漠然とした不安も、少しずつ大きくなっていきました。
転機となった学会発表
—— 転機となった出来事について教えてください。
博士課程で初めての学会発表に挑戦しようとした時が、一つの転換点だったと思います。
ある日突然、涙が止まらなくなって、胸がすごく苦しくなりました。机に突っ伏したまま、何もできない状態になってしまったんです。学会発表の準備どころではなくなり、大学院にも行けなくなりました。努力してもできないことがあるんだという現実に直面して、入院を経験しました。これが抑うつ状態の始まりでした。
—— 当時どのような心境でしたか?
学会発表をキャンセルするまでは、自分は努力すれば何でもできるんだと思い込んでいました。でも、努力してもできなかったという経験が、逆に「ずっと頑張り続けなければいけない」という思考から解放してくれたんです。辛い経験でしたが、今振り返ると、これが回復への第一歩だったのかもしれません。
支えとなった主治医・カウンセラーとの出会い
—— 治療を受けるまでの経緯を教えてください。
嘔吐がなかったので、ただ食べ過ぎているだけだと思っていました。病気だなんて考えもしなかったし、苦しいと言ってはいけないような気もしていたんです。ファスティングや民間療法も試したんですが、全然効果がなく…。そこで初めて「病院に行ってみよう」と思い立ちました。
主治医との出会いも、最初からうまくいったわけではありませんでした。3人目の先生でようやく、私の話をちゃんと聞いてくれる方に出会えたんです。ストレスが溜まると、それを掻き消すような苦しさを自分に与えたくなるんですが、あからさまな自傷行為は勇気が出なくてできないから、代わりに自分を苦しめる手段として「薬を飲まないようにしよう」と考えます。当時は薬を飲まないと心臓が抉られるかのような痛みを感じていたので、自分を十分に苦しめることができました。そんな思考も含めて、その先生は受け止めてくれました。
—— カウンセリングはどのような影響がありましたか?
特に大きかったのは、カウンセラーとの5年間の関係性です。ちょっとした様子の変化も敏感に感じ取ってくれて、「なんでそう思うの?」と問いかけてくれて、私のことを理解しようとしてくれました。メールでのやり取りなども通じて、自分の気持ちを整理する助けになりました。
一人で抱え込んでいた気持ちを安心して話せる場所があるのは、本当によかったなと思います。
回復への道のり 自分の現状を受け入れることの大切さ
—— 現在の状況はいかがですか?
食生活も落ち着いて、抑うつ状態も改善傾向にあります。通院しながらの薬物療法も継続中です。でも正直なところ、調子が悪い時ほど自分を虐めたくなって、薬をやめて自分を苦しめたくなることがあります。むしゃくしゃして自分を痛めつけたくなります。ただ、飲まないと涙が出てきたり胸が苦しくなったりするのはやっぱりしんどいので、薬の大切さも実感しています。
今も、完全に回復したわけではないんです。毎年夏頃になると少し拒食気味になって、BMIが17くらいまで落ちることもあります。でも最近は「これ以上痩せたらまずい」と思って自分でコントロールできるようになってきました。
—— 回復の過程で大切だと感じることはありますか?
「頑張りすぎなくていい」ということを少しずつ受け入れられるようになったことが大きいです。完璧を求めすぎず、自分の現状を受け入れることの大切さを、時間をかけて学んでいる最中です。完璧にできないと落ち込むこともありますが、それでも自分を責めすぎないように心がけています。
同じ痛みを抱える人たちへ
—— 同じような状況にある方に、何か伝えたいことはありますか?
まず、一人で抱え込まないでほしいです。話せる人に話すだけでも、本当に楽になります。自分の苦しみをわかってくれて、しっかり話を聞いてくれる人を見つけるのは簡単ではないかもしれません。でも、どこかに必ずそういう人はいるんです。「きっと自分を理解してくれる人がいる」と思っているだけでも、少し楽になれると思います。カウンセリングも一つの選択肢です。
それから、「病気で苦しいんだ」と自分の現状を認めてあげることも大切だと思います。回復の道のりに決まった正解はありません。完璧を求めすぎずに、自分のペースで、自分に合った方法を見つけていってほしいです。
すんさんとお話してみたい方へ
すんさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。