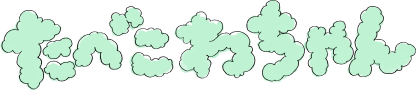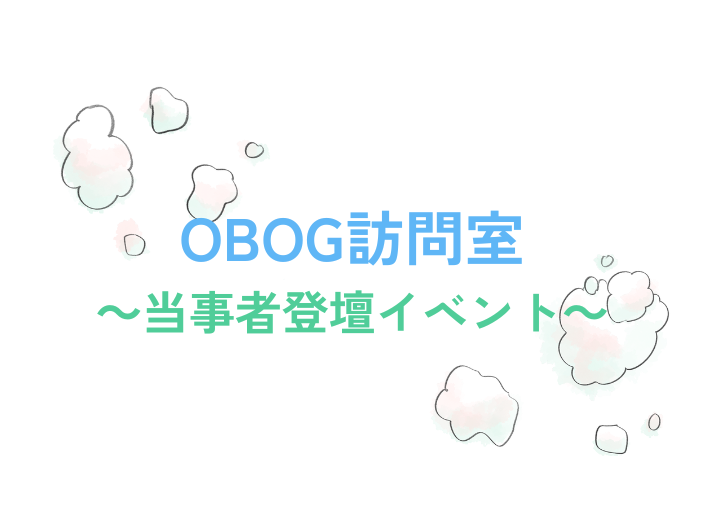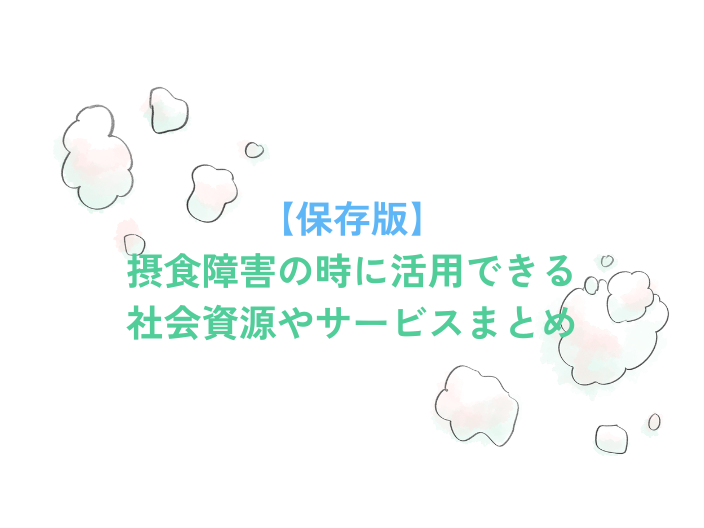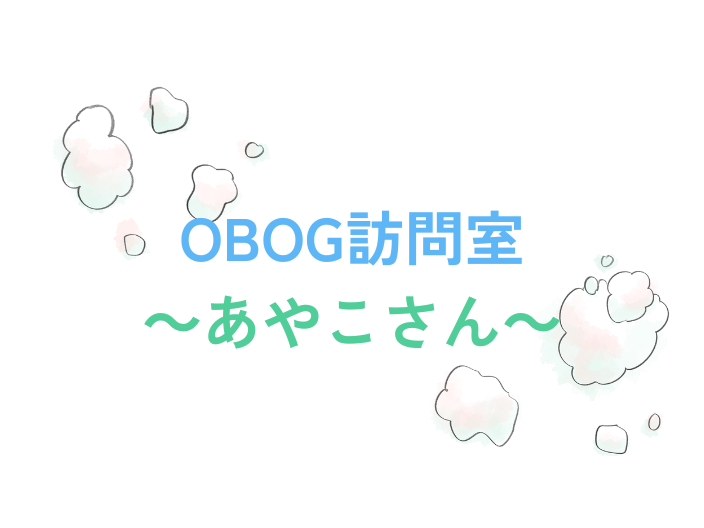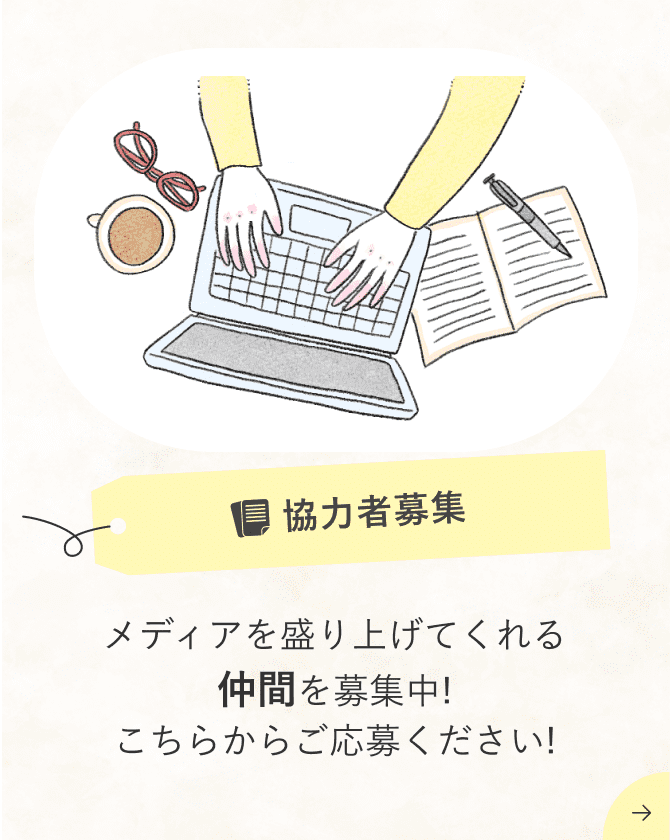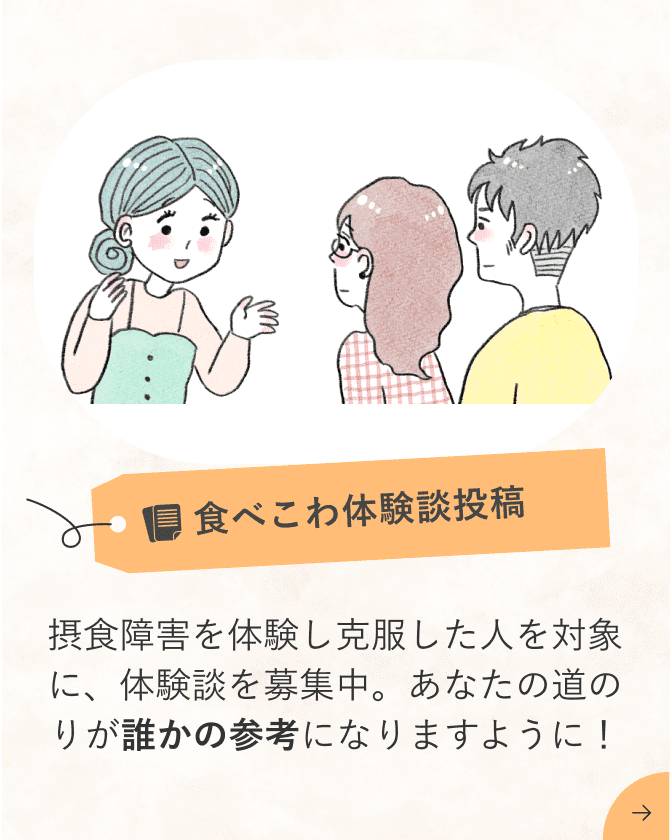高校時代、ダイエットをきっかけに始まった摂食障害
—— 摂食障害が始まったきっかけを教えてください。
周りの子たちより体が大きかったこともあり、小学生の頃から自分の体型を気にしていました。でも、本格的にダイエットを始めたのは高校1年生の時でした。きっかけは、男子が「太った子は嫌い」と話しているのを聞いてしまったことです。その時はすごくショックで…。さらに、当時付き合っていた人からも「細い女性が好き」と言われました。そういう言葉が重なるうちに、「自分も痩せないといけない」と思うようになっていったんです。
—— ダイエットはどのようにエスカレートしていきましたか?
完璧主義な性格も相まって、どんどん制限を強くしていきました。
母親が心配していたので、「1日1800kcalは摂取する」という約束をしたんです。でも、その数字に縛られ過ぎてしまって。目玉焼きの油をティッシュで拭き取ったり、食べ物を細かく刻んで少なく見せたりしているうちに、体重がどんどん落ちていきました。周りの友人からは「痩せすぎて怖い」と言われるようになったんですが、自分では全然そう思えなかったんです。鏡を見ても、「まだ痩せ足りない」としか感じられなくて…。今思えば、感覚が麻痺していたんだと思います。
—— その頃、どのような心境でしたか?
周りから心配されるうちに、だんだん罪悪感も感じるようになりました。「私が食べないと、みんなが不幸になる」という考えが頭に浮かぶようになったんです。でも、食べないといけないと分かっていても、食べるのが怖くて。そんな矛盾した気持ちに挟まれて、ますます食事の時間が辛くなっていきました。家族と一緒に食卓を囲むのも、本当に苦痛でした。
30年間の紆余曲折 ー 拒食、過食、そして自殺企図まで
—— その後、症状はどのように変化していきましたか?
その後の30年間は本当に長い道のりでした。拒食と過食を行き来しながら、受験、就職、転職、結婚、育児を経験しました。一番辛かった時期には、薬のオーバードーズによる自殺企図もしました。
最初は拒食だけだった症状が、数ヶ月で過食に変わってしまったんです。下剤も使うようになって、当時流行っていたダイエットティーも大量に飲んでいました。母に「食べてほしい」と言われて仕方なく食べた後、罪悪感に耐えきれなくて結局下剤で出してしまう。そんなサイクルを繰り返していました。
—— 結婚後も症状は続いたのですね。
はい、結婚後も症状は続きました。特に妊娠中は大変でした。カロリー計算が止められなくて、体重がなかなか増えなかったんです。「赤ちゃんに栄養が届いているのかな」と悩んだ時期もあります。そんな時、産婦人科の先生が「赤ちゃんは勝手に栄養を吸収するから大丈夫よ」って声をかけてくださったんです。その言葉にどれだけ救われたか..。今でも先生には本当に感謝しています。
—— 育児中はいかがでしたか?
育児中も大変でした。夜中や休みの日、一人になると制御が効かなくなることがあったんです。菓子パンを一気に食べた後、大量の下剤を使う。そんな日々が続いていました。でも、その時間だけは誰にも邪魔されない、本当の自分でいられる時間だったんです。辛い現実から逃げて、自分を慰めていたのかもしれません。過食することが、私にとって生きるために必要な習慣のようになっていました。
症状がひどくなるにつれて、人間関係も怖くなってきました。友人を作るのも避けるようになったんです。周囲の人は私を理解しようとしてくれていたんですが、時々「なぜ病院に行っても治らないの?」と言われることもありました。責められているわけではないとわかっていても、やっぱり辛かったです。過食と下剤の使用は、20代から40代まで続きました。外にも出られず、家の中でずっと過食を繰り返していた時期もあります。
転機となった「理解者」との出会い
—— 転換点となった出来事があったそうですね。
数年前、仕事で出会った先輩との出会いが転換点になりました。実は高校時代、学校に行けない日は家でずっと料理本を写していたんです。それをずっと「学校をサボっていた」と感じて、自分を責め続けてきました。でも、その先輩は「それって写経と同じことだよね。きっと心を落ち着けるためにやっていたんだね」と言ってくれたんです。誰にも話せなかった過去をそんな風に受け止めてもらえた時、本当に救われました。
—— その出会いはどのような変化をもたらしましたか?
その先輩は、私の話をよく聞いてくれて、いつも温かい言葉をかけてくれました。「あなたのやりたいようにやっていいんじゃない?」と言ってもらえた時、ずっと自分を責めていた気持ちが少し楽になったんです。
子どものころから、困っている人の役に立ちたいという気持ちがありました。でも、自分の状態がこんなだから、全然人の役に立てていないと思っていました。それが、その先輩に出会ってから、もっと自分にもできることがあるんじゃないかと思うようになったんです。そんな想いを抱いた時、大きな決断をしました。夫のもとを離れ、転職をするタイミングで転居することにしたんです。新しい土地で、新しい生活を始めることにしました。
子どもの食の課題から見えてきた新たな気付き
—— 子育ての経験からも気づきがあったそうですね。
そうなんです。うちの子は、ミルクも飲まず、離乳食もあまり食べず、食物アレルギーもありました。周りの人は心配して「今日は何グラム食べた?」「体重は何グラム増えた?」と聞いてくれるんですが、中には「お母さんの作る食事が美味しくないんじゃない?」と言う人もいました。私自身、食の支援に関する資格を取得していたこともあって、「どうしたら自分の子が食事をとってくれるんだろう」と、ずっと悩んでいました。
—— その後、ご自身の考え方に変化はありましたか?
子どもが赤ちゃんの時は、食べられるものが本当に限られていたんです。3種類ほどしか食べられなくて。でも、色々なものを食べられるように練習していく過程で、「この子なりのペースで食事がとれるようになれば良いんじゃないか」と思えるようになりました。
そして、子どもが少しずつできることを増やしていく姿を見守るうちに、自分自身への視線も変化していったんです。「私も私のペースで進んで良いんじゃないか」。そう思えるようになりました。
同じ痛みを抱える人たちへ
—— 現在のお仕事について教えてください。
現在、子どもたちの発達に関わる仕事をしています。仕事をする中で、今では「摂食障害の経験も無駄じゃなかった」と思えるようになったんです。摂食障害になってからの道のりは本当に大変で、回復までこんなに長くかかるとは思いませんでした。でも、この経験があったからこそ今の仕事に出会えたし、悩んでいる子どもたちの気持ちもわかる。回り道だったかもしれないけど、この道を歩んできたからこそ今の自分がいるんだと感じています。
—— 現在も症状と向き合っているのでしょうか?
カロリー計算は今でも続けているんですが、それも「自分の特性」として受け入れられるようになりました。無理にやめようとするのではなく、自分には必要なことだと認めて、うまく付き合う方法を見つけたんです。「今日はおやつを食べたから、夕食を少し軽めにしよう」とか、そんな風に柔軟に調整しています。新しい土地での生活が始まってからは、誰の目も気にしなくていい場所で、自分のペースで食事をすることができているんです。それだけで、だいぶ気持ちが楽になりました。
—— 同じような状況にある方に、何か伝えたいことはありますか?
本当に長い間大変でした。でも、この経験があったからこそ、今の仕事で子どもたちの気持ちを深く理解できているんだと思います。もし摂食障害で悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひお話を聞かせてください。私の経験が少しでもお役に立てるなら嬉しいです。
人それぞれ、どんなきっかけで気持ちが変わるかわからないものです。時間はかかるかもしれませんが、きっと自分なりの答えが見つかると思います。
のんさんとお話してみたい方へ
のんさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。