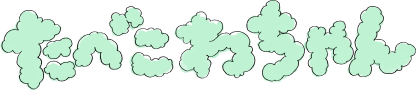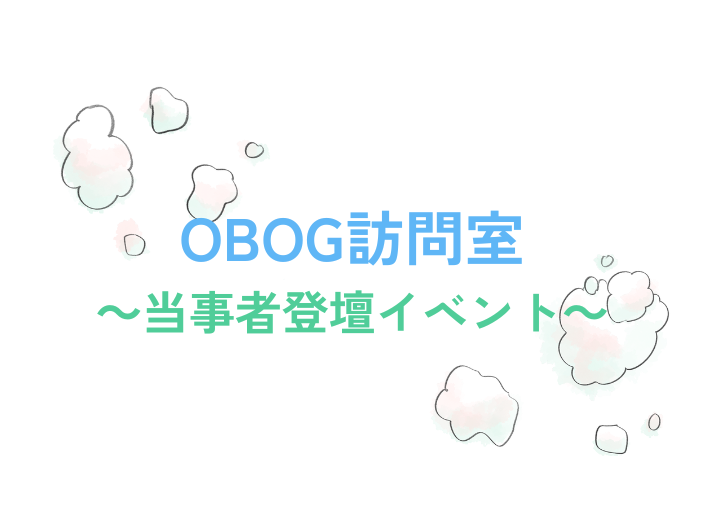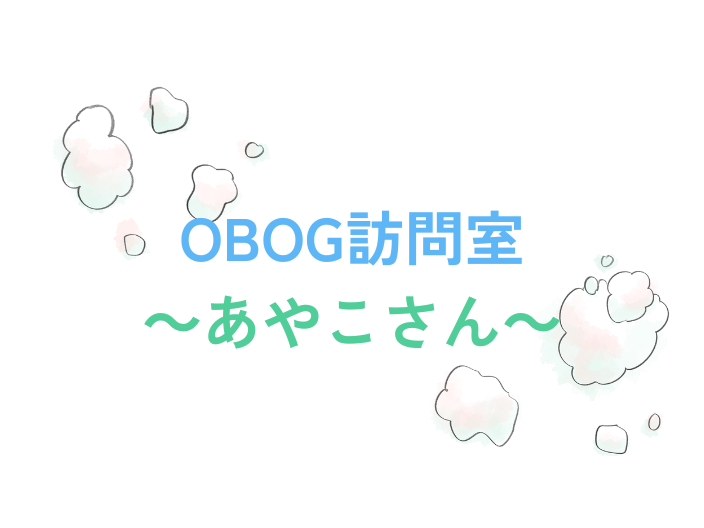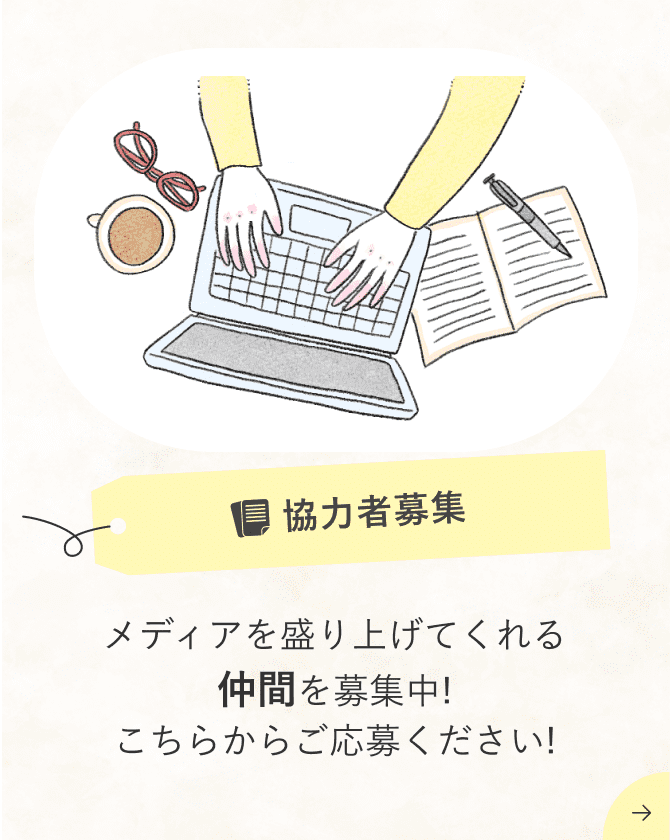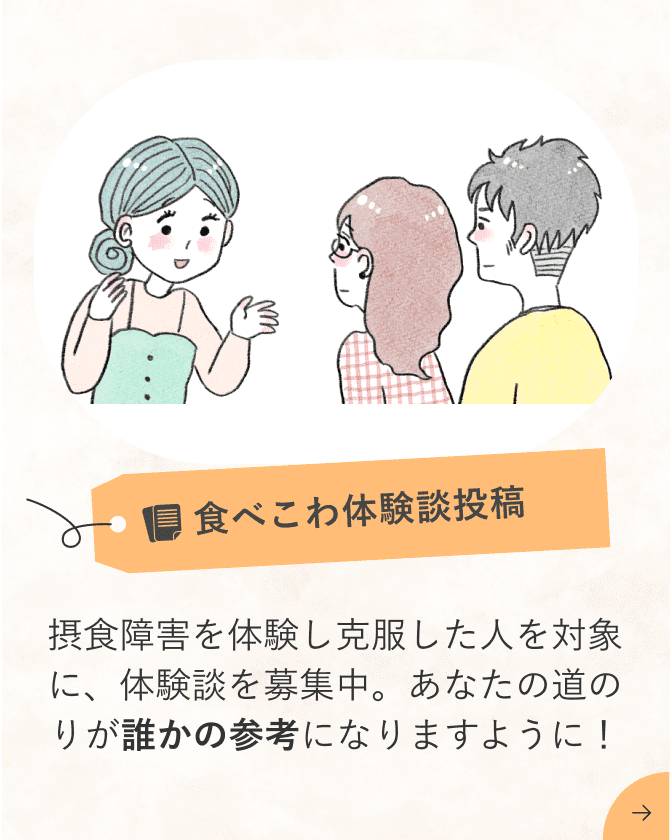「頑張らなければ」から始まった制限
—— 摂食障害が始まったきっかけを聞かせてください
中学生の頃は、何かを頑張らないと自分がいてはいけないような気持ちが強かったんです。両親の不仲もあり、母はいつも仕事と家事の両立で疲れているように見えました。だから自分がしんどいとか、寂しいとか、本当はこうしてほしいという気持ちがあっても、それを言ったら母の負担が増えてしまうと思って。「迷惑をかけたくない」という思いから、自分の気持ちを押し殺して生活していました。
学校でも、自分に対してすごく厳しくしていました。自分の中で納得できていない成績をもらう三者面談では、よく泣いていた記憶があります。誰かに言われたわけではなく、頑張らないと、結果が残せていないと駄目だと思い込んでいたんです。
—— そんな中で、食事制限が始まったのはいつ頃でしたか?
中学1年生の冬から2年生の春頃です。当初はよくあるダイエット目的だったんですが、体重が減ることへの達成感と、痩せた私を見て周りの人が心配してくれることが嬉しくて、徐々に自分にかける制限を強くしていきました。
症状が重くなった結果、半年以上の入院を経験することになりました。体の状態が本当に悪くて精神科の病棟では受け入れてもらえず、小児科での入院になったんです。そのとき入院していなければ死んでしまっていたと思うから、入院した意味はあったと思います。でも、その後、気持ちが落ち込むたびに「なんであのとき助けてくれたんだろう。私はそれを望んでいなかったのに。」と思うこともありました。
大学時代に現れた過食の症状
—— 大学進学後、症状に変化はありましたか?
大学での生活自体は充実していました。児童養護施設でのボランティア活動をする部活に入って、素敵な仲間たちと出逢ったり、バイトをしたりしていました。そんな中で飲み会に参加したり、友達と食事に行ったり、大学入学当初は食べることが楽しかったんです。でも、過去に食事制限をしていたこともあってか徐々に過食が始まり、悪化していきました。
当時辛かったのは、自分で自分をコントロールできない無力感でした。見た目も変わってきて、人に会うのが怖くなりました。体力も消耗するし、精神的にもしんどかったです。大学3年生の頃には抑うつ状態になって、休養という目的で入院しました。
—— その入院が転機になったのでしょうか?
転機となったのは、入院先で主治医から言われた「自分の感情に気づきましょう」という言葉でした。最初は全く意味がわからず、「感情に気づくって、どういうことですか?」というところからスタートしました。
それまでの私は、つらい出来事があると「死にたい」という言葉でまとめて表現していたんです。その間にある感情、例えば寂しさとか悲しさとか、そういった感情を全部スキップしていきなり「死にたい」という言葉になっていました。
—— 感情を言語化する練習はどのように始めましたか?
最初は本当に意味がないと思っていました。でも主治医に言われ続けるので、仕方なくやってみていました。感情を表す言葉を一つひとつ調べて、自分の中にある感情を言語化する努力を続けていたんです。
担当の医師が代わっても同じことを言われるので続けていたら、今は大分自分の感情を言語化するのが得意になりました。劇的に変化したというほどではありませんが、自分の感情を言語化することができるようになってからのほうが、摂食障害の症状や精神的な不調が減ったような気がします。
一人暮らしでの苦悩と転換点になった仲間との出会い
—— 一人暮らしを始めたのはいつ頃ですか?
社会人になって少し経った頃です。実はその頃、家族と些細な喧嘩をしたタイミングで、再度入院することになったんです。その時は両親に入院のことを伝えなかったんですが、なぜか私の中では連絡が来ることを期待していて…。でも結局、両親からの連絡がなかったことに傷ついて、一人暮らしを決意しました。
振り返ると、家族は私にどう接していいかわからなかったんだと思います。でも、当時の私は体調があまり良くなかったこともあり、そんなふうに理解する余裕がありませんでした。今では、家族とは適度な距離感で付き合っています。期待もしないし、期待しないからそんなに傷つくこともない。物理的な距離があることで、かえって落ち着いた関係を保てているんじゃないかなと思います。
一人暮らし自体はなかなか難しかったですね。一人暮らしを始めてから過食嘔吐の症状が悪化することもあったんですが、同時に過食嘔吐の大変さを改めて感じることもありました。お金もかかるし、ゴミ捨ても面倒だし。こんなことをいつまで続けるんだろう、と思うようになりました。
—— その後、摂食障害を隠したい過去ではなく受け入れられるようになったきっかけは?
大きな転換点となったのは、同じような経験を持つ仲間との出会いでした。精神疾患と付き合いながらやりたいことをやっていたり、自分の道で輝いている人たちに出会ったんです。摂食障害だからどうこう、ではないんだと思えるようになりました。
そう思うようになってから、以前は誰にも話せなかった摂食障害の経験を徐々に話せるようになりました。食事の場面で気を使われるのが嫌で、ずっと言えなかったんです。でも今では大学時代の友達にも、「実は摂食障害だったんだよ」と話せるし、自分の状態を説明して、相手にどうしてほしいかも伝えられるようになっています。
ゆるやかな希望を抱いて
—— 現在、摂食障害の経験をどのように捉えていますか?
私の経験が誰かの参考になればいいなとは思います。でも、誰かを救わなければとか、そういうことは考えていなくて。自然体でいられる範囲で、もし役に立つことがあればという気持ちです。
病気になったからこそわかることもあるし、病気になったからこそつながれた人もいる。せっかく経験したことだから、何かに活かせたらいいなと思うようになりました。
過食嘔吐の症状は今も完全には消えていません。でも、その捉え方は大きく変わりました。今は、症状を何とかしようと躍起になることはなくなったんです。治ったらいいなという思いは持ちつつも、無理に変えなければと自分自身を追い詰めることも少なくなりました。ストレスや疲れで症状が出ることもありますが、それも含めて自分なんだと受け止められるようになりました。
—— 最後に、今後についてお聞かせください
完全に治ることを目指すというより、症状があってもうまく付き合いながら生活していけたらいいなと思っています。「あ、これって無理しすぎてるな」とか、「今日はしんどいな」とか、そういう自分の状態に気づけるようになったことが、一番の変化かもしれません。
回復までの道のりは一直線じゃないと思うんです。だからこそ、少しずつでも前に進んでいければいいんだと今は思っています。
なつきさんとお話してみたい方へ
なつきさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。