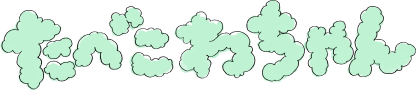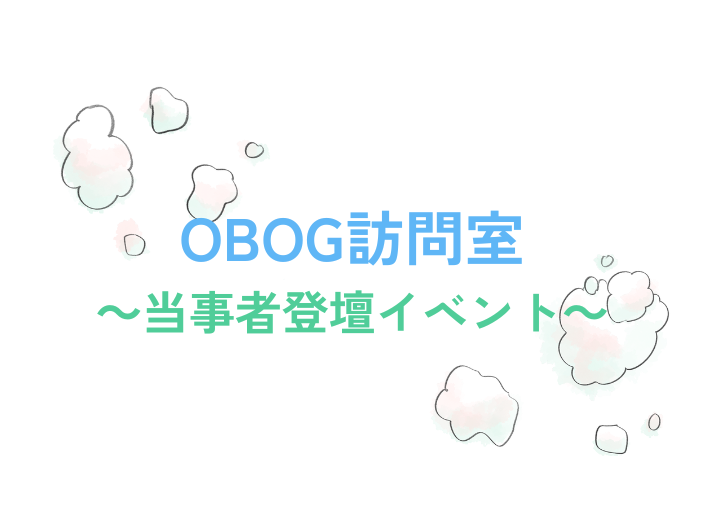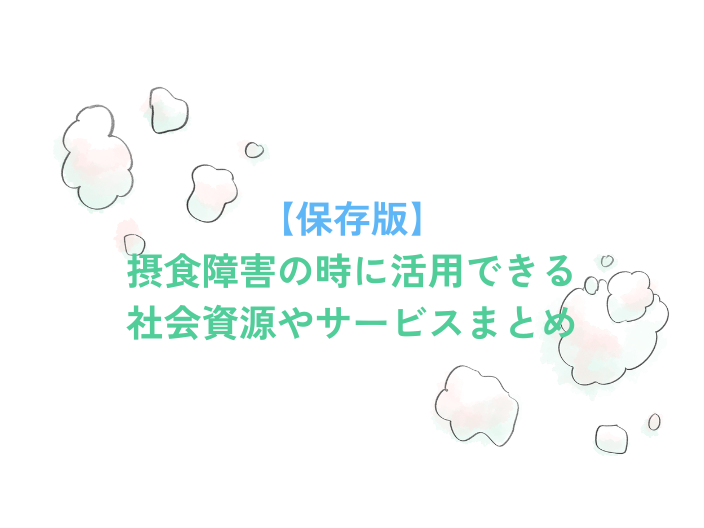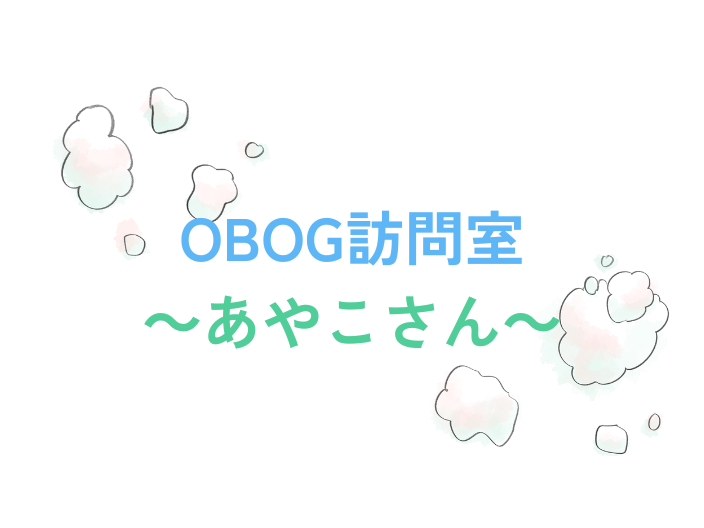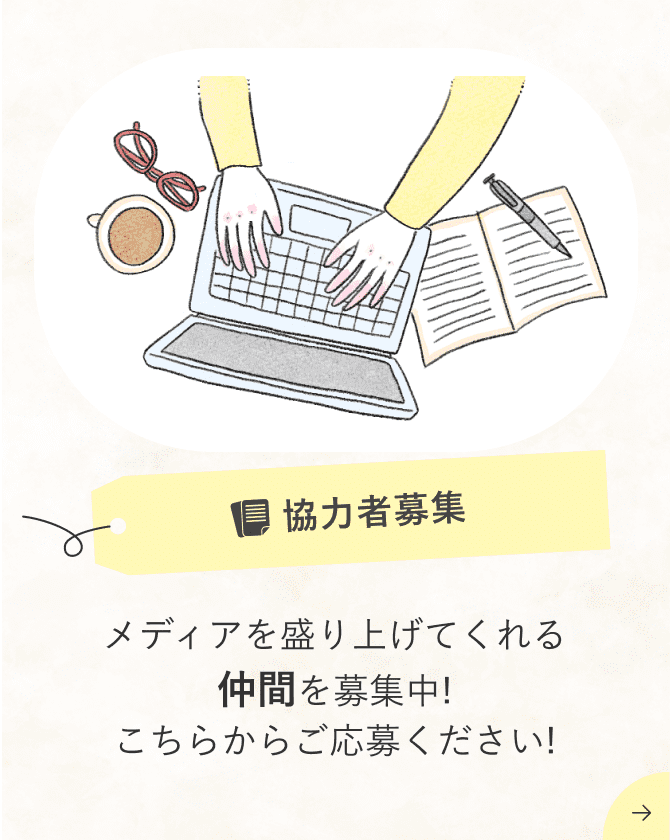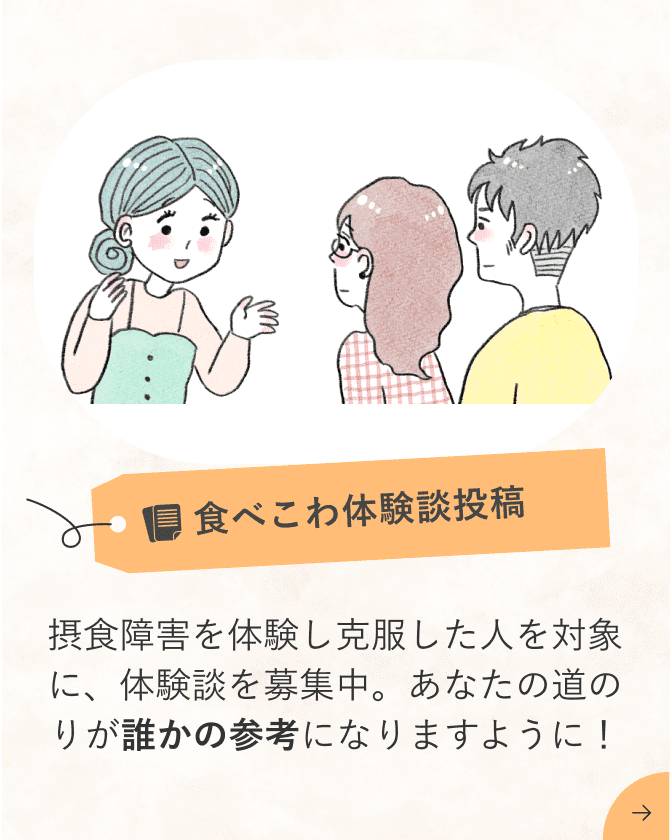小学生から始まった家族のケア
—— 体重やボディイメージについて気にかけるようになったきっかけはありますか?
最初のきっかけは小学校3、4年生のことだったと思います。その頃から不登校になりました。それで母が小児心療内科に連れて行ってくれたんですけど、当時の私にとって先生は「何を話したらいいんだろう?」という感じの人でした。母の方がメインで話していた記憶があります。
そんな中で、今思うと不健康なんですけど、体重が減っていることを認められるのが少し嬉しかった時期がありました。当時、病院の先生との話題がなくて困っていたんです。でも体重のことについて話すと、自分に関心が向いたような感じがして。自分の話題ができたことが嬉しかったのかなと思います。
実は家族の中では、色々と複雑な状況がありました。今でいうヤングケアラーじゃないですけど、小さい頃から家事をしたり、母の話を一晩中聞いたりしていました。母はうつ病で、母自身が幼い頃に祖母からネグレクトを受けていた過去がありました。そういう重い話を、10代前半の私がずっと聞いていたんです。父との関係も難しかったです。普段はあまり話さないんですけど、怒り出すと物に当たったり、何日も口をきかないことがあって。そういう精神的な暴力というか、それが母の病気や家族全体の関係にも影響していたと思います。
—— ご家族との関係が摂食障害に影響したと感じますか?
そうですね、きっと大きく影響していると思います。家族のことは色々あって、それが心理的に影響して、食べなくなってしまったのかなと。当時から、自分のことに集中できない感覚があったり、人生を生きている気がしなくて…ずっと家族のためにサポートをしていました。
祖母が入院した時には、病院に一緒に行ったりもしていました。区切りとして、祖父母が亡くなったのがちょうど20歳過ぎくらいなんですけど、それから自分の摂食障害に向き合って、自分も働きたいけどどうしようみたいな話とか、ようやく自分の話ができるようになりました。
学校という居場所の難しさ
学校のことでいうと、小学生から不登校で、中学にはほとんど行きませんでした。通信制の高校にも行ってみたんですけど、半年くらいでやめてしまったんです。フリースクールも試してみましたが、結局合わなくて通うまでには至らなくて…学校って何だろうということは、ずっと考えていました。
去年、就労移行支援というところに通って、履歴書を書く機会があったんです。その時に、履歴書を見てみると「中退」で終わってしまっていて。実際は本を読むのが好きだったり、数学も高校の時にやっていたりしたんですけど、それが紙の上では全然伝わらないんですよね。ショックというか、社会に対してちょっとした怒りのような感情を感じて、それで高卒認定を取ろうと決めました。8科目を一気に取ることができました。
診断名を聞いて安堵した日
—— 摂食障害だと知ったきっかけについて教えてください。
身長は160センチ以上あるのに、10代後半くらいから体重が40キロを切ってしまいました。周りからも摂食障害じゃないかみたいな話をされていましたね。
20歳くらいの時に、病院の先生から摂食障害と言われたんです。それまではそういう認識がありませんでした。摂食障害という名前を聞いたことはあったんですけど、やっぱり吐いたりするイメージが強くて、私は吐いてないから違うんじゃないかなと思っていました。
でも診断名を聞いた時は、はっきりした感じがして嬉しかったんです。ずっともやもやと悩んでいたことに「あ、そういう名前がちゃんとあるんだ」と思って。それがきっかけになって、家族の関係についても「ここからちゃんと直して、自分のことをやっていこう」と考えられるようになりました。
—— 診断に対してどう向き合い始めたのですか?
摂食障害という診断名がついたことで、自分の状況がはっきりした感覚がありました。それから障害者支援の現場を見る機会も増えて、社会的な偏見を目の当たりにすることも多くなりました。就労支援のA型やB型事業所でも、スタッフとの関係で困っている人を見たり、上下関係みたいな嫌な部分も見えて、そういう経験から社会問題に興味を持つようになったんです。
父に涙ながらに訴えた夜から始まった家族の変化
—— その頃、ご家族とはどんなやりとりがありましたか?
当時、家族療法を受ける機会がありました。家族療法といっても本当、少し先生と話したというだけなんですけど。いつも母と私だけで行っていたところに、父を連れていくことになったんです。
父にそれを話した時のことは、今でもよく覚えています。ある日、私が夕食にカレーを作っていた時に、家族療法に来てほしいという話をしました。そうしたら父が激昂して、私の作ったカレーをゴミ箱に捨ててしまったりしたんです。気性が激しいところがあるので、そうなるだろうなとはわかっていたんですけど…。涙ながらに父に訴えて、やっと来てもらったという感じでした。
——お父様に病院に来てもらうのは、勇気がいることだったのでは?
家族の中では母と私の距離だけが近くなってしまって、家族の中でも孤立していると感じていました。母とは何でも話すという感じだったんですけど、父とも状況を共有する必要があると思ったんです。私が働いたり病院に通ったりするには、父の理解も必要だなと感じて。
家族療法の場で、「自分のせいで娘が病気になったんじゃないかと思って」と言って、父が泣いていました。それに向き合うのが父は辛かったのかなと…。それから父が車で送り迎えをしてくれるようになったり、家で一緒にご飯を食べなくて良くなったり、それで私も精神的にだいぶ楽になりました。
「ここまでやらなくていいんだ」という気づき
その後、デイケアに通うようになったんです。最初はケースワーカーさんとただ話すという感じだったんですけど、他にもプログラムで料理を作ったり、一緒に散歩したりすることもありました。最初はそういうプログラムには参加していなかったんですけど、デイケアで開催されている陶芸や茶道などの習い事をするうちに、徐々に通い始めたという感じです。
——デイケアではどんなことを学びましたか?
私の祖母は統合失調症を患っていたんですが、それもあって、障害を持っている人と関わる中で、自分の中にも偏見があったんだなと気がつきました。
あとは、自分の何でも家族に捧げてしまったり、人のために自分を顧みずに何かをやってしまう傾向に、他の人と触れ合うことで「あ、ここまでやらなくていいんだ」と気づけたりもしました。10年くらいかかったんですが、色々な記事を見たりもして、やっとこんな風に思えるようになりました。今働けているのも、デイケアのような場所に行くことで練習になったのかなと思います。
体力づくりから一般就労へ
—— 現在はどのように過ごされていますか?
4年前に一度アルバイトをしたことがあったんです。その時は主治医から体力的に大丈夫かと心配されながらも働いていて。今度はもっとちゃんと時間をかけて仕事を探したくて、就労移行支援に通いました。そこのスタッフさんと少し合わなくてやめてしまったこともあったんですけど。
今所属しているA型事業所は自分でホームページで探して見つけた場所で、短時間から体力づくりのような感じで働いています。来年くらいに一般就労ができるといいなと思っています。
手帳は確か就労移行支援に通う時に取ったので、2~3年前くらいだったと思います。診断は不安障害と摂食障害の2つです。
—— 今後について、やってみたいことや取り組みたいことがあれば教えてください
今一番興味があるのは、ジェンダーやフェミニズム、政治の分野です。そういう本を読んだりしていて、働きながら月1回講座にも通っています。摂食障害は特に若い女性に多いと思うんですが、家庭環境や学校という閉じられた空間で、辛いことがあっても、行く場所が家庭と学校しかないんですよね。そういう状況で女性が不利益を被っているのを見ると、何とか良くならないかなと思うんです。あとは、自分が子供らしい子供時代を過ごせなかったこともあって、「一人一人が自分らしくいられる社会」はどうしたら実現できるんだろうということも考えています。
実際に仕事を探す時に、そういう関心もあって福祉関係の仕事が向いているかなと思ったりもします。自分の経験を生かして、それを仕事にするのもいいと思うんですけど、自分にとってそれが本当にいいことになるのか、頑張りすぎてしまって結局別の病気になってしまうのかなとか…そんな心配もあって。一方で、ボランティア活動や講座への参加、自分で勉強することなんかは、必ずしも仕事にしなくてもできることなのかなとも思うんです。これについてはまだ迷っている部分です。
仕事以外のことで言うと、人との距離の取り方について考えていきたいです。人と話すのも嫌いじゃないんですが、関わりすぎると疲れてしまうこともあります。人との最初の話の段階で、境界線みたいなものの見当がつくようになったので、それを人によって変えていく、自分で調節ができるようになっていったらいいのかなと思っています。
ルッキズムへの考え方
今でも完全には抜け出せていないのが、ルッキズムの考え方です。
母と一緒に出かけることが多くて、その時に歩いている女性の見た目について、母がネガティブなことを言うことがありました。寝たきりだった母と比べて、そういうことを言えるくらい元気になったというバロメーターの1つだったのかもしれません。当時は「なぜそんなこと言うんだろう」と思っても言えなかったんですけど、最近は母にも対等に「言わなくてもいいんじゃない」と言えるようになってきたんです。
ただ、そういう母の言葉を聞いて育った分、私にもその影響は残っています。見た目で人を比べてしまったり、見た目を気にする自分が嫌いになったり。刷り込まれているものは簡単には変わらないと思うんですけど、それも徐々に楽になればいいなと思っています。
——お母様との関係で変化を感じることはありますか?
昔から、母と私が対等じゃないという認識はあって、自分が子供であるということに対して違和感を持っていました。家の中では私が家事をして母の話を聞いて、なのに外に出ると学校に行ってない子供として私は振る舞って、親として母が振る舞うという、そういう逆転みたいな状況が、すごく苦しかったです。
子供であるのに子供でいられなかった時間が自分の中にあるからこそ、若さを謳歌している人を見ると、少しモヤモヤしてしまったりもします。
それは自分の考えと母の考えがまだ混ざってしまっている部分があるからだと思うんです。それをちゃんと切り分けて、自分だけの考えを持ちたいなと思います。だいぶちゃんと分かれてきたというか、私は私という風に前より思えるようになってきたと思います。
同じ痛みを抱える人たちへ
——同じような経験をしている人に伝えたいことはありますか?
最近気づいたことなんですが、摂食障害や家族のケアをしている人にとって「孤立」という部分が、あまり話題にならないなと感じています。周りの人が「大変だね」と声をかけてくれないと、自分では大変な状況だと気づきにくいと思うんです。
誰かのケアをせざるを得ない状況って、同世代の友達には話しづらいんですよね。そういう話題で盛り上がるわけでもないし、相談できる大人も身近にいなくて。そうやって孤立してしまうことを、なかなか言葉にできない人も多いと思います。
だからこそインターネット上の情報や、同じような経験をした人の体験談に触れることで、「自分だけじゃない」と気づけることは大事なことだと感じています。自分のせいじゃないんだよということに、少しでも気づけるきっかけがあればいいなと思っています。