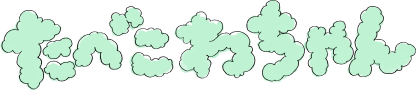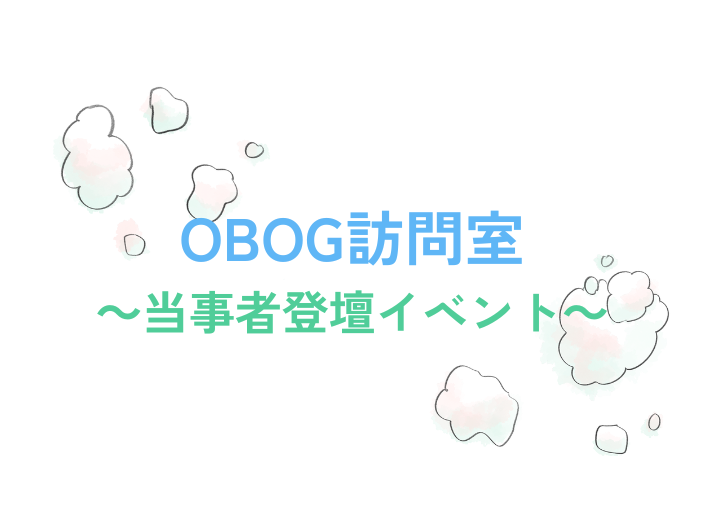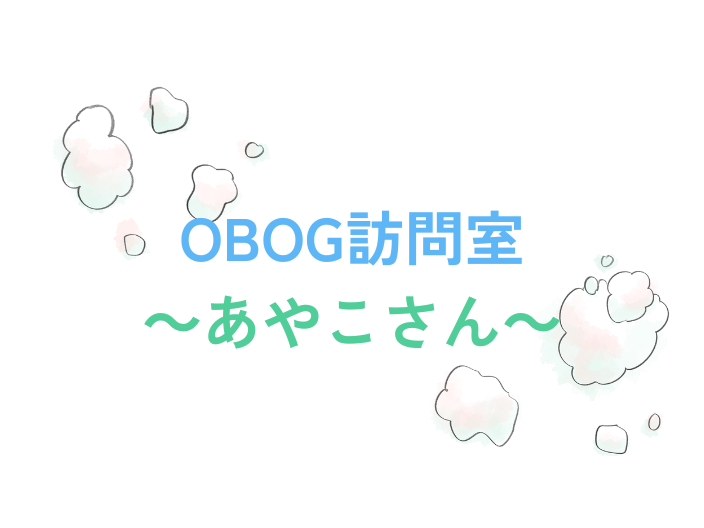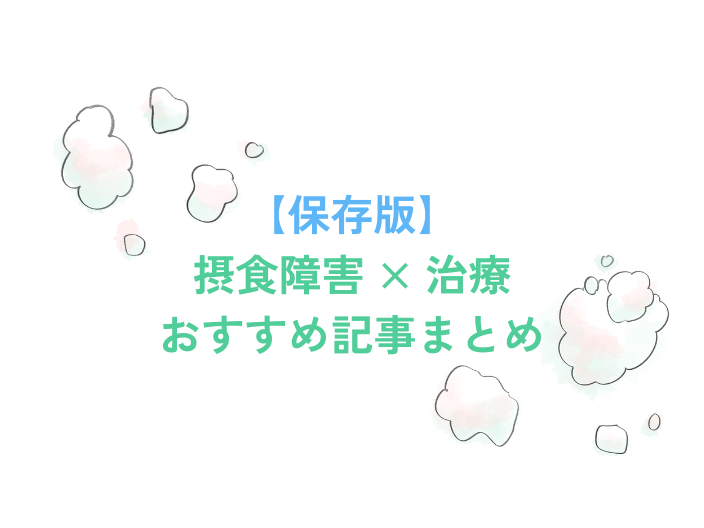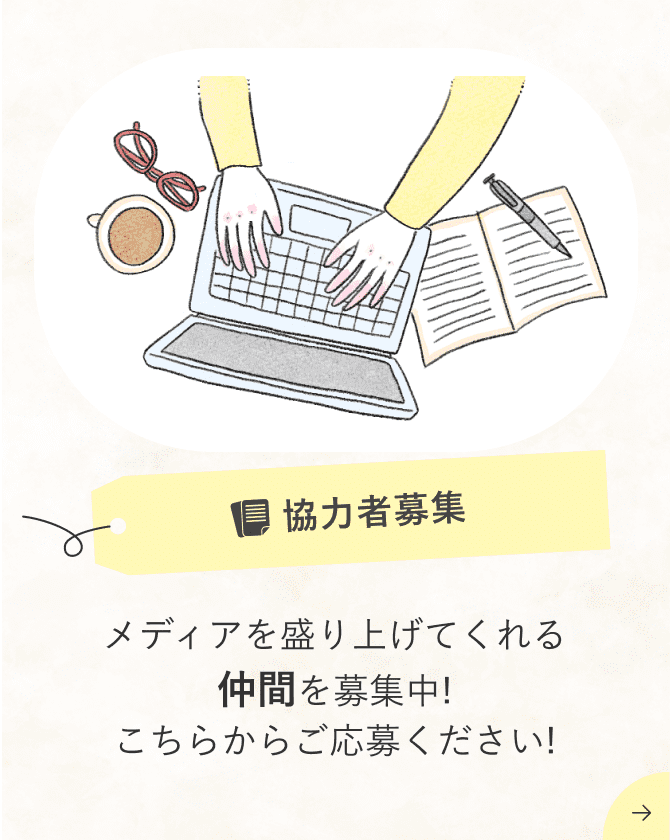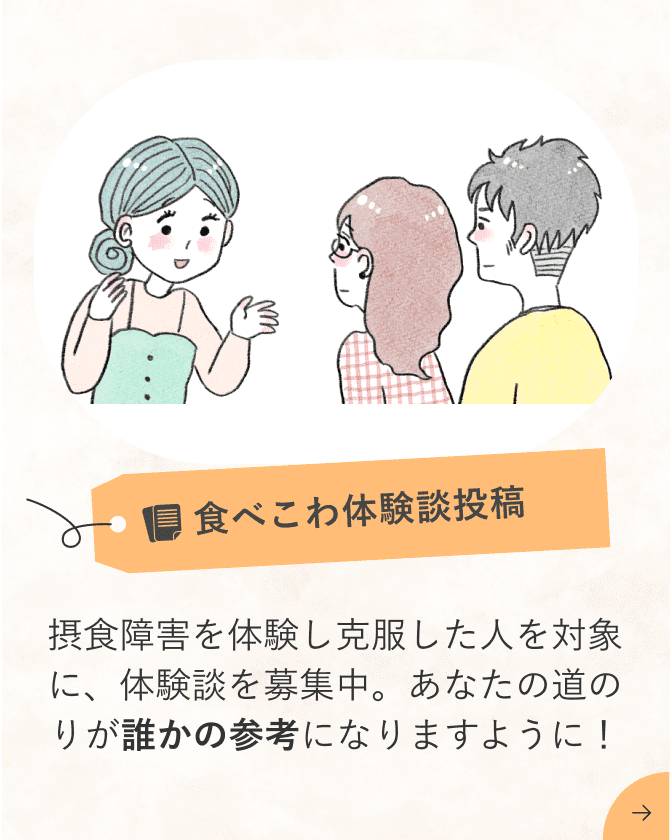安心できなかった家という場所
—— 幼少期や学生時代はどのようなお子さんでしたか?
中学時代は家庭環境が複雑で、家にいても心から安心できない状況でした。両親の仲が悪く、母の精神状態はあまり安定していませんでした。これが理由で、幼い頃から「お母さんを支えないと」と思いながら過ごしていたんです。当時はそれが普通だと思っていましたが、今振り返ると、子どもの頃の私には負担になっていたんじゃないかなと思います。
母の考えと違うことを言うと否定されることが多くて、「自分が間違っているのかな」といつも思っていました。もやもやした気持ちや、罪悪感をずっと抱えていたんです。
当時は「お母さんが怒るのは私が悪いからだ」「私がもっとしっかりしていれば、家族はうまくいくはず」と、自分を責めていました。でも今思うと、子どもが家族の問題を背負う必要はなかったんですよね。もっと早く「これは私のせいじゃない」って気づけていたら、あんなに自分を追い詰めずに済んだかもしれません。
部活での減量が拒食のきっかけに
—— その後、摂食障害の症状が始まったきっかけを教えてください。
陸上部に入り減量を始めたことが、摂食障害のきっかけになったと思います。顧問の先生が友達に「そんな身体じゃ強くなれない、もっと絞らないと」と言っているのを聞いて、「自分も体重を落としたら速くなるかも」と思ったんです。
—— 最初はどのような気持ちでしたか?
減量を始めた当初は、純粋に競技力をあげたいと思っていました。でも、家で自分の気持ちを抑えることが多かったからか、徐々に「自分の身体だけは私がコントロールできる」という感覚が生まれてきたんです。体重が減っていくと達成感があって、その感覚にどんどんはまっていってしまいました。
中学3年生になった頃には、全速力で走れないくらい体力が落ちていました。それでも体重が増えることが怖くて、減量をやめることができませんでした。冬になるとすごく寒くて、制服に裏地をつけてもらっていました。夜も空腹と寒さで眠れず、睡眠導入剤を処方してもらったりもしていたんです。食事制限も、最初は肉を魚に変えたり、揚げ物を避けたりする程度だったのが、どんどんエスカレートしていって…。
食事の量も細かく計るようになりました。お腹がすいたとか、疲れたとか、そういう体からのサインを無視して、自分で決めたルールを優先するようになっていったんです。
受験期の危機感が転機へ
—— その後、状況が変わるきっかけはありましたか?
受験期のある日、数学の問題を解いていたら、急に頭が真っ白になったんです。数字は見えていて、解き方も分かっているのに、頭の回転がすごく遅くなりました。低血糖だったと思うんですが、その時に本当に怖くなって…。「このままじゃ危ない。受験も乗り切れないんじゃないか」と、初めて危機感を感じたんです。その危機感から少し制限を緩めて、なんとか高校には合格できました。高校時代は、中学生の時と比べると、食事に対する不安が少なくなっていたと思います。
その後、大学は栄養学部に進むことにしました。自分の体験を理解するためにも、栄養について学びたいという気持ちが出てきたんです。
—— 大学進学で環境が変わったのですね。
環境の変化が良い方向に働きました。高校までのように時間割が全て決まっているのではなく、自分のペースで過ごせるようになったことが大きかったと思います。友達と楽しく過ごす時間を大切にしたいと思う中で、「これくらいなら食べても大丈夫かな」と考えられるようになったんです。精神的に余裕ができたことで、食事に対する見方も変わっていきました。
それまではご飯の量を必ず計っていたんですが、大学に入ってから、その制限を少しずつ緩めていくことができました。「今日はよく動いたから、いつもより多めでもいいかな」と思えるようになったり、食べた後も「まあいいか」と受け入れられるようになっていったんです。精神的なゆとりがあると、食事に対しても柔軟になれるんだなと実感しました。完璧を目指すのではなく、その時の自分ができる範囲で食べられるようになっていったんです。
管理栄養士を目指すようになったきっかけ
—— 管理栄養士を目指すきっかけになった出来事を教えてください。
学生時代、保健センターの管理栄養士さんに相談したことがありました。体重を増やさないといけないのは分かっていたんですが、闇雲に増量するのは嫌で、何をどのくらい食べたらいいのか具体的に知りたくて相談に行ったんです。
でも、「何を食べたらいいですか?」と聞いたら、「何でもいいですよ」って言われて。今振り返ると、きっと「食べられるものなら何でもいいから、とにかくしっかり食べて欲しい」という意味だったと思うんです。でも私が欲しかったのは、「朝はこれくらい、昼はこんな内容で」という具体的なアドバイスでした。どんなものをどのくらい食べたら健康的に体重を増やせるのか、それが知りたくて相談に行ったのに「何でもいい」と言われて、どうしていいか分からなくなってしまったんです。
——その時はどのような気持ちでしたか?
やっと相談できる場所を見つけて、勇気を出して行ったのに、悩みを分かってもらえなかったような気持ちでした。具体的なアドバイスが欲しかったのに、曖昧な答えしかもらえなくて…。その経験から「栄養について自分でしっかり学んで、同じように悩んでいる人の力になりたい」と思ったんです。今度は自分が、誰かの気持ちに寄り添える存在になりたいと思いました。
栄養教諭として働く中で分かった、自分なりの調整方法
—— 実際に栄養教諭として働き始めて、いかがでしたか?
最初は、給食を食べることに抵抗感もありました。給食には普段避けていた食材や調理法のものも入っていて、量も私には多く感じられたんです。最初は「この量を食べても大丈夫かな」と不安になることもありました。でも、生徒たちに「給食をしっかり食べましょう」と指導する立場なので、自分が食べないわけにはいきませんよね。その責任感もあって、覚悟を決めて食べるようになりました。
ただ、「毎日この量を食べ続けたら体重が増えちゃうかも」という心配もありました。それは嫌だったので、給食はきちんと食べつつ、夕食で調整したり運動を増やしたりして、自分なりにバランスを取るようにしていました。
—— 現在はどのような食生活を送っていらっしゃいますか?
中学生の頃から続けてきた食事の工夫が、今になって役立っています。運動のタイミングや食事の時間など、これまで色々試してきた経験を活かして、自分に合った調整方法を見つけられました。お昼は生徒と一緒に給食をしっかり食べて、夜は体調に合わせて調整しています。例えば、遅い時間の食事では炭水化物を少し控えめにして、タンパク質中心にしたりとか…。ランニングも、以前は体重を減らすために無理をしてでも走っていたけど、今は純粋に楽しめるようになりました。
同じ痛みを抱える人たちへ
—— 現在の摂食障害との関係をどう捉えていますか?
食事に振り回されることは、昔に比べてかなり減りました。でも摂食障害と完全に縁が切れたわけではないと思っています。食べることに抵抗を感じる時もまだあるんですが、そういう時の乗り越え方や、自分に合ったペースが分かってきたというイメージです。環境が変わったらまた新しい付き合い方を見つけていく必要があると思いますし、完璧を目指すより、その時々の自分に合った方法を探していくことの方が大切だと感じています。
—— 同じように悩んでいる人に向けて、伝えたいことはありますか?
「その時の自分に合った付き合い方」を見つけることが本当に大切だと思います。私も沢山試行錯誤しました。色々な方法を調べて、試して、悩んで…。当時は本当に苦しかったんですが、今思えばその経験が私の力になっています。回復までの道のりは人それぞれ違います。「これが正解」というものはないので、それぞれが自分のペースで、自分なりの方法を見つけていければいいと思うんです。
時間はかかるかもしれないけれど、そのうち「まあいいか」と思える瞬間がきっと見つかります。完璧じゃなくても、今できることから始めていけば、少しずつ前に進めるはずです。
mikanさんとお話してみたい方へ
mikanさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。