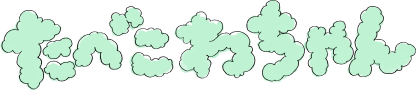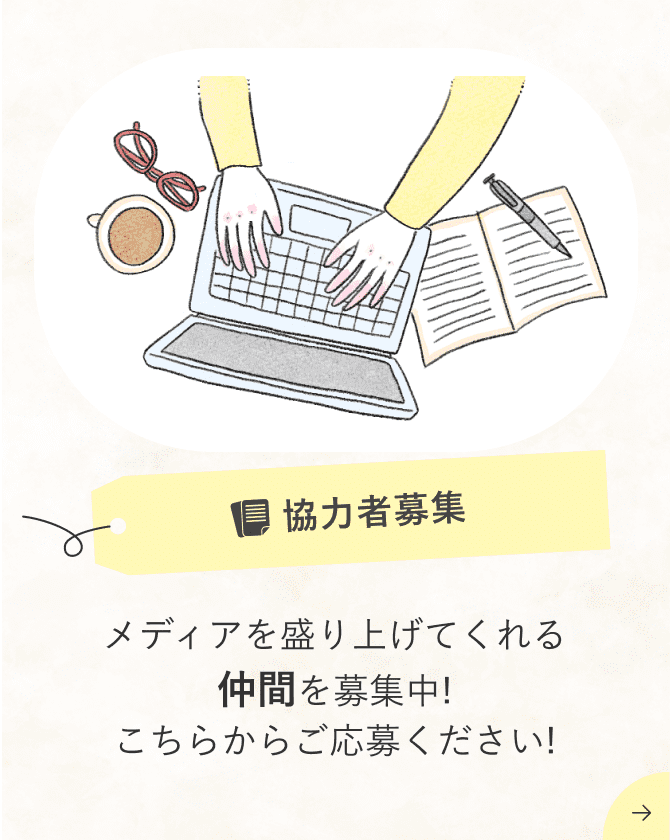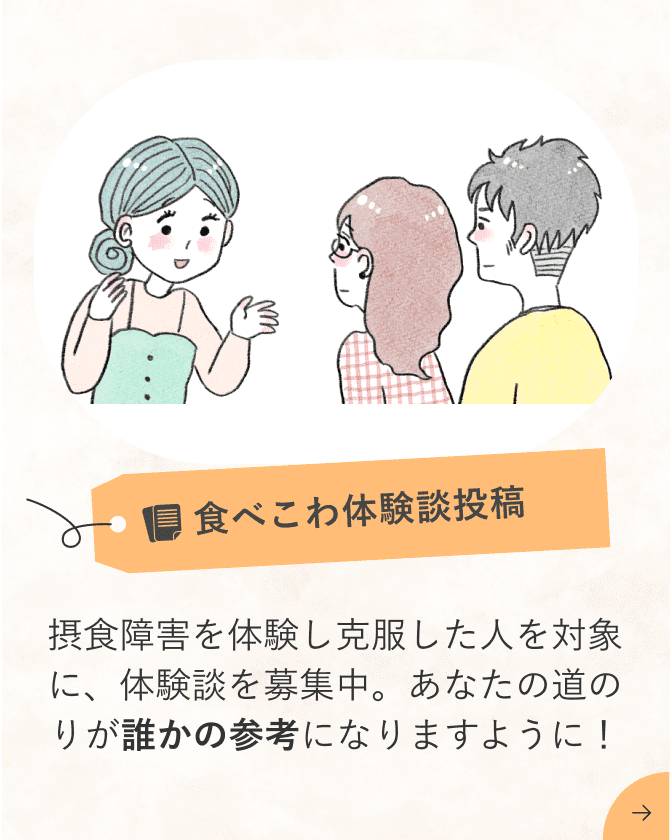小学5年生から始まった娘の変化
── 娘さんに最初の変化を感じたのはいつ頃でしたか?
小学5年生の頃でした。娘が体型を気にし始めた当初は「年頃の女の子だからダイエットしたいのかな」と思っていました。実は、この時期に大きな環境変化が重なっていたんです。夫の両親との同居を機に引っ越しをして転校。さらに娘にとっての弟が誕生したことなど、生活環境が大きく変わった時期でした。母親として生活に追われる中で、少しずつ細くなっていく娘の変化に気づきながらも、どう対処してよいかわからない日々が続いていました。
中学1年生になると、娘の食事は野菜中心になって、だんだん食べる量も減っていきました。11月頃からは学校への登校も難しくなっていて。心療内科を受診したところ、当初は適応障害と診断されました。
──病院探しはどのように進みましたか?
病院探しにはとても苦労しました。初診まで何ヶ月も待たなくてはいけない病院が多かったんです。その後、ようやく地域の総合病院の心療内科につながることができました。当時はまだ、摂食障害だとは知りませんでした。
それでも症状は良くならず、娘が「気合いを入れないと起き上がれない」と言うようになったり、血圧が下がって体が動かないといった状態も続いていました。そんな状況で、娘の方から「入院したい」と言い出したんです。ところが、いざ入院が決まると「やっぱり入院したくない」と気持ちが変わってしまって…。娘は嫌がっていたんですが、体調が悪化していたため、最終的には入院せざるを得ませんでした。
二度の入院と家族の葛藤
── 最初の入院について教えていただけますか?
入院してからも、娘は一時期、食事を完全に拒否していました。その3ヶ月間は経管栄養で過ごすことになりました。小児科の先生方も頭を抱えていて、転院も検討されました。そんな時に、たまたま東京から来ていた先生が「この子はいつか、きっと食べられるようになる」と言ってくださったんです。その先生の言葉に励まされたのか、娘も少しずつ食べ始めるようになりました。
病院での生活は娘にとってストレスが大きかったと思います。面会時間が限られていたり、食後は一人で過ごさなければいけなかったり、スマートフォンも使えなかったり。そういうストレスが、私に対してぶつけられることもありました。
娘の入院生活で一番つらかったのは、外出や外泊の後に病院に戻る時でした。「帰りたくない」と大泣きする娘を連れて、病院に帰らなければ行けなくて。看護師さんたちも困った様子でしたし、母親としてもとても辛い時間でした。
── 2度の入院を経験されたとのことですが、何かきっかけがあったんでしょうか?
いったん退院し自宅療養の生活に戻ったものの、高校受験期に症状が再発しました。娘は話すことが少し苦手だったので通信制高校を考えていたんですが、高校に入学する前の面談で「話せない子は取りません」というようなことを言われてしまって。それがとてもショックだったようで、また食事が取れなくなってしまい、2度目の入院となりました。
── 高校進学後はいかがでしたか?
高校には入学できたものの、9月に退学することになりました。そして10月には祖父が亡くなって。その頃から、過食嘔吐の症状が出始めました。おじいちゃんっ子というわけではなかったけれど、二人でいるだけで心が落ち着く、そんな関係だったと思います。お互いに多くを語らなくても、一緒の空間にいると安心できるような存在だったようです。
祖父の死は、娘の心に大きな影を落としました。長期の入院治療で食事への抵抗が薄れ、3食をきちんと摂れるようになっていた矢先の出来事だったんです。祖父の死をきっかけに過食嘔吐を発症し、体重が再び減少していきました。
母として見出した向き合い方
── 長年の経験を通じて、どのような気づきがありましたか?
娘の場合、ずっと0か100だったんです。過食嘔吐をやるかやらないか、その中間がない。そんな娘の特徴を理解していく中で「無理に止めなくていいから」と、少し距離を置いて見守るようになりました。以前、過食嘔吐を辞めると決めた時に娘がすごく不安定になったことがあるんです。その時の様子があまりにも辛そうで。それを見て、私も考え方を変えました。今は、娘が自分のペースで気持ちを落ち着かせられるよう、見守ることを大切にしています。
── 現在はどのように過ごされているんでしょうか?
娘本人は、体調が悪い時に病院で点滴を受ける程度の治療を続けています。母親の私は、定期的に病院でカウンセリングを受けているんです。カウンセリングをしてくれる先生は私たちの状況を色々な角度から分析してくれるので、新しい気づきがあります。私だけでは見えない視点で助言をもらえるのが助かっています。
また、1-2ヶ月に1回の頻度で訪問看護も利用しています。これも娘本人ではなく、私自身が看護師と話す機会として活用しているんです。看護師さんには、最近の様子を報告したり、困っていることを相談したり。第三者の視点からアドバイスをもらえるのが心強いんです。
──現在の娘さんの状況と、お母さんの心境の変化を教えてください。
摂食障害や過食嘔吐の症状を抱えていても、社会とうまく関わってくれればいい。完治にこだわらず、症状と付き合いながらでも、娘が人生を楽しんでくれたら良いなと思います。それが私の娘に対する今の願いです。
現在、娘はアルバイトをしながら、自分なりのペースで生活を送っています。一番症状が重かった時期は、精神的に不安定になると過食嘔吐の回数も増えて、色々と大変でした。でも今は、日常生活の一部になっているというか、「今日は辛いから過食嘔吐をしちゃおうかな」という感じで娘なりに付き合えるようになってきています。
同じ痛みを抱える人たちへ
── 同じような状況にある方に、何か伝えたいことはありますか。
母親として、SNSでの情報発信や交流も積極的に行ってきました。お母さん同士でつながったり、時には当事者の方の気持ちを聞いたり。オンラインでもオフラインでも、理解してくれる仲間がいることで救われました。そんな中で、やっぱり一人で抱え込まないことが大切だと気がつきました。誰かに話すだけでも楽になることがあると思います。
もちろん家族だからこそ気づけることもあります。うちの娘も、言葉では表現できなくても、泣いたりして何かを訴えようとしますから。でも、家族との関係が難しい場合もありますよね。一番身近な家族が理解者になれればいいけれど、そうできないこともある。そんな時は、友達でも、SNSで知り合った人でも、誰でもいいので誰かに話してみて欲しいと思っています。
まりこさんとお話してみたい方へ
まりこさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。