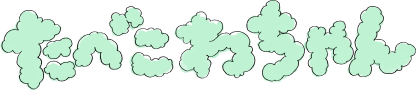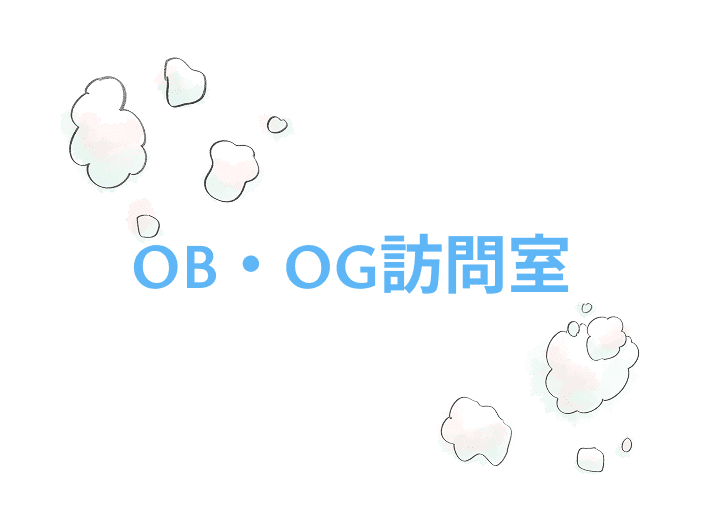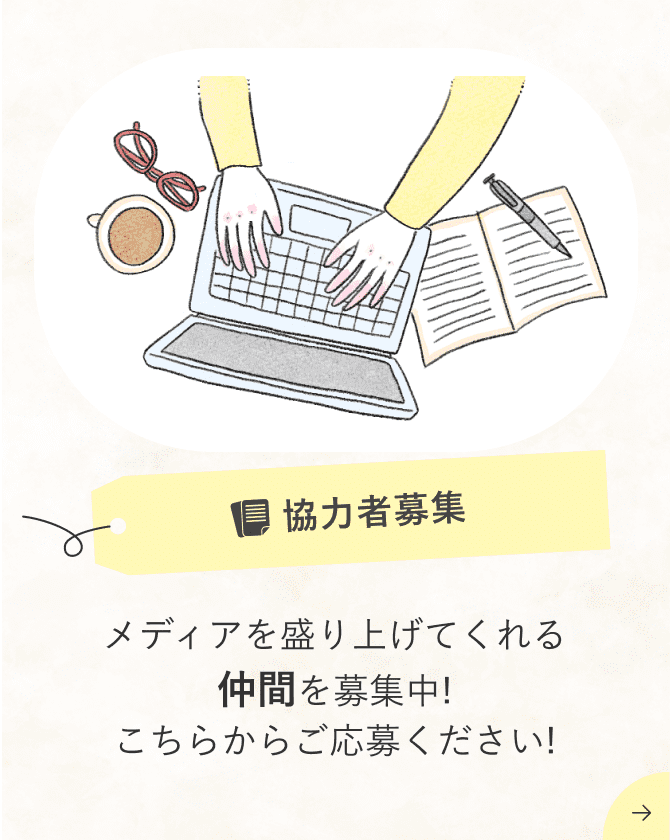「痩せたね」から「痩せすぎかも」へ——異変に気づいた瞬間
異変を感じ始めたのは、中学2年生の途中。最初は「痩せたんだな」という印象でしたが、徐々にその変化は明らかになっていきました。
顔の骨が浮き出て見えること、足が驚くほど細くなっていること。そして学校を休むようになったこと。小さい頃から知っている幼馴染だからこそ、「このままだと危ないのではないか」と強く感じました。
私は当時、摂食障害という病気の存在を知っていました。だからこそ、「もしかしたらそうなのかもしれない」と頭の中で結びついていきました。
「話したい」と思ったときには、もう遅かった
私がが強く意識していたのは、「普段と変わらないように接すること」。あまり気にしすぎると、その心配が相手に伝わってしまうのではないか。それが逆効果になるのではないか。そう思っていたからです。
同時に、「痩せたね」という言葉は絶対に口にしないようにしていました。その一言が、「もっと痩せなきゃ」「もっと痩せたい」という気持ちを強めてしまうかもしれないと感じていたからでした。
本当は、どこかのタイミングでしっかり話をしたいと思っていました。でも、いざ話そうと思ったときには、すでになつきさんは「正常な状態」ではなく、十分に話せる状況ではありませんでした。
「あの時、もっと早く話を聞いてあげられたら」その思いは、今でも後悔として残っています。
本人には言えなくても、先生や親に相談
あの時は、大切な友達だからこそ、自分自身も精神的にとてもつらい時期だったと思います。早く元気になってほしい。会いたい。話したい。そう思いながらも、どうすることもできない感覚がありました。
そのつらさは、先生や親に相談していました。一人では抱えきれなかったし、相談することで自分も落ち着きたかったと思っていました。
また、異変には気づいていたものの、本人にそのことを伝えることはできませんでしたが、当時の担任の先生には相談していました。
友人としてできることに限界を感じながらも、「誰かに繋がらなければ」と思っての行動でした。
同じ立場の人へ伝えたいこと
振り返ってみて思うのは、「もっと早く話を聞いてあげたり、寄り添ってあげたかった」ということ。当時の自分には、「遠慮や戸惑いはせず、思ったことは伝えるべき」そう伝えたいです。
それでも、中学生の自分にできる、専門家でなくてもできる行動として、「一人で抱え込まずに、周囲に相談する」ということがあったと思い返しています。
当事者も、その周りの人も、とてもつらい経験をすると思います。でも、その経験を通して「命の大切さ」を強く感じることも事実です。
気づいた時点で、気にかけること。一人で抱え込まないこと。それは、専門家でなくても、そばにいる人だからこそできる大切な関わりなのかもしれません。
「心配だけど、どう接したらいいか分からない」そう感じているのは、決してあなただけではありません。迷いながら、戸惑いながら、それでも気にかけていること自体が、すでに大切な関わりの一つです。
そしてもし可能であれば、少しだけ勇気を出して、話を聞く姿勢を示してみること。それが、後になって「できてよかった」と思える関わりになるかもしれません。
本人(なつきさん)からのコメント
幼馴染であり、小中学校を一緒に過ごし、中学では生徒会活動も共にしていた彼女が、当時私のことを心配して担任の先生に何度も相談してくれていたと後から知りました。
あの頃の私は自分のことで精一杯で、周囲がどれほど気にかけてくれていたかに気づく余裕がなく、お礼も言えないまま卒業してしまったことが心残りです。けれど「もっと早く話を聞いてあげたかった」と言ってくれたその言葉に、申し訳なさ以上に、見ていてくれたことへの温かさを感じました。
中学生という未熟な時期に、友達のことで悩み、大人に相談するという選択をしてくれたことは、本当に簡単なことではなかったと思います。
私は中学生活の半分ほどを同級生と同じようには過ごせず、担っていた役割も果たしきれなかったという思いから、周囲に迷惑をかけたのではないかという引け目をずっと抱えてきました。そのため、当時親しかった友人たちと疎遠になっていったことも「当然だ」とどこかで思っていました。それでも、時間が経った今もこうして関係を続けてくれている友達がいることに、深い感謝の気持ちがあります。