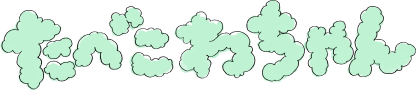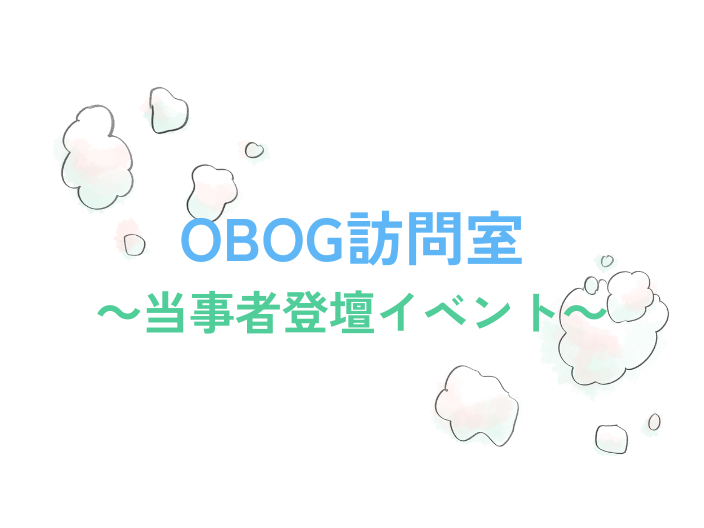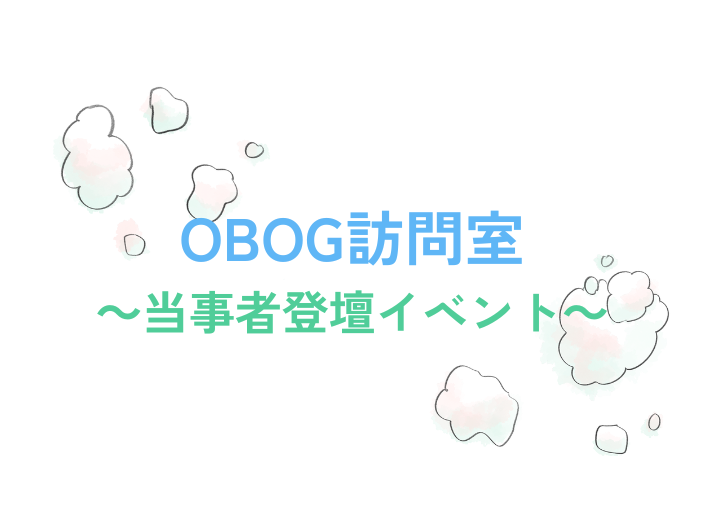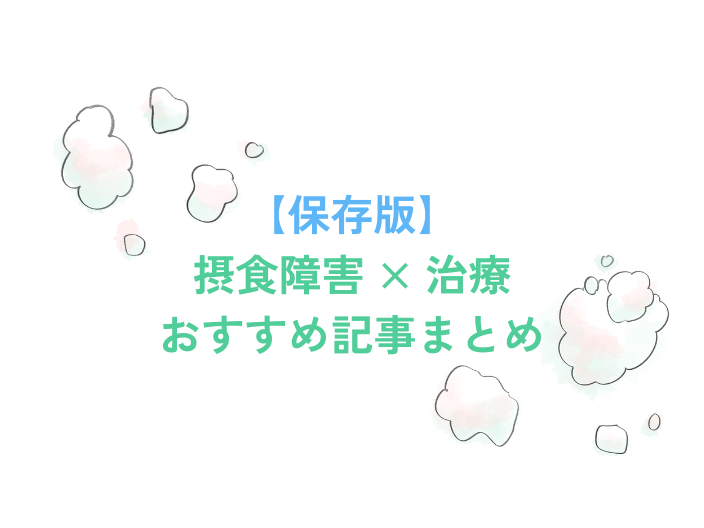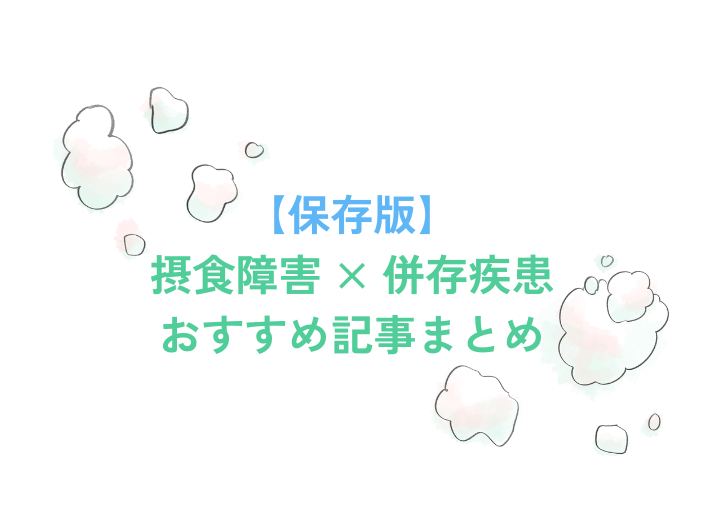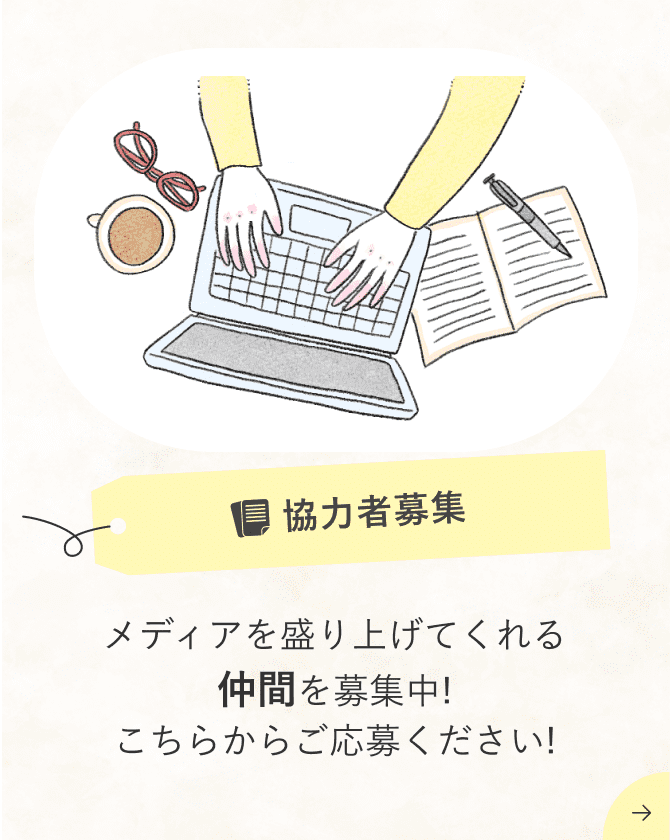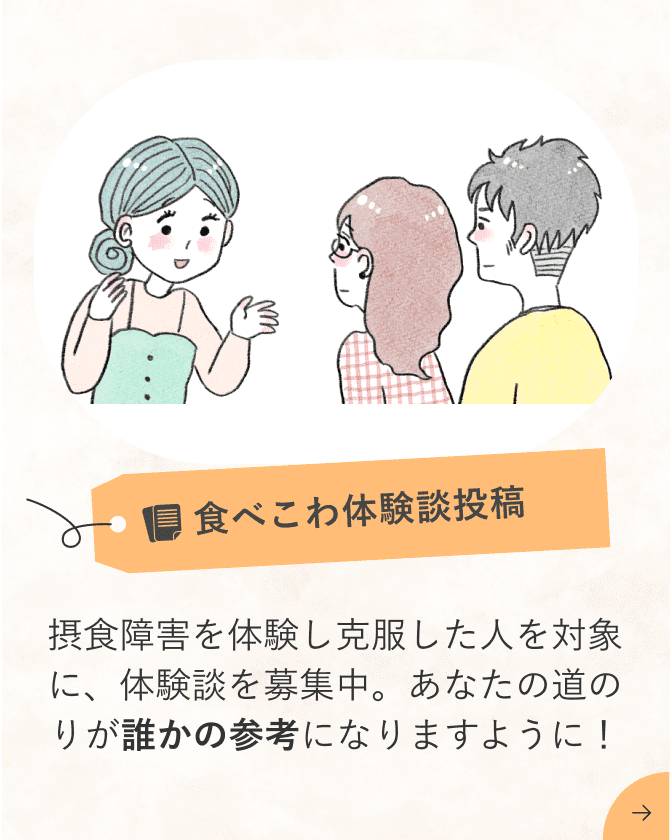登壇者紹介
――今回ご登壇いただく専門家は、山内常生先生です。現在は医療法人微風会浜寺病院の副院長で、摂食障害の専門医師として外来・入院ともに多くの患者さんを診てこられました。治療の質をより高めようと、症状や食事の記録をつけられる「パーソナルヘルスレコードアプリ」の開発にも関わるなど、積極的に取り組まれている先生です。
それでは当事者のすんさんに、自己紹介をお願いできますか?
すん:すんといいます。今回は摂食障害と発達障害、両方の経験を持った当事者として登壇させていただきます。
簡単にこれまでの摂食障害や発達障害との付き合いをお話しすると、20歳くらい、大学生の頃にダイエットをきっかけに拒食が始まりました。当時は病識がなく、痩せられてラッキーという感じでしたが、徐々に過食に移行し、体型の変化で悩むようになりました。
一度社会人として働いた後、大学院に戻った時期が一番症状が酷くて、病識も持ち始めて通院やカウンセリングを始めました。ストレス要因を取り除く中で、少しずつ症状が緩和していったように思います。
その治療過程で、摂食障害専門のカウンセラーさんに出会い、症状が落ち着いた頃に「もしかしたら発達障害の傾向があるんじゃない?」と言われ、知能検査を受けました。その結果、確定診断ではないんですけれども、ASD、自閉スペクトラム症の傾向があるというように言われました。
現在は、通院やカウンセリングを続けつつ、抑うつの症状もあったので、思考の癖を自覚・改善したり、コミュニケーションや対人関係に関する自己理解を深めるために精神科のデイケアに通ったりもしています。
本日はよろしくお願いします。
発達障害の特性は、摂食障害の発症や、長引いたり悪化したりすることに繋がる?
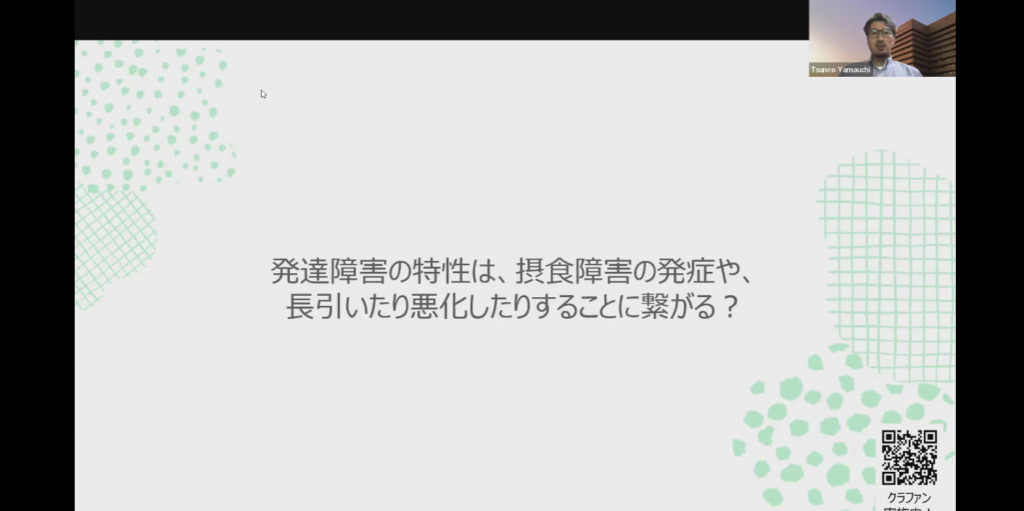
――発達障害の特性は摂食障害の発症や悪化、長期化に関係があるでしょうか?
すん:そうですね、私の場合は吐かない過食だったんですが、過食以外の普通の食事、いわゆる人と一緒に楽しく食べるような食事や、ちゃんと主食・主菜が揃った食事が怖くて受け入れられないというのが強かったです。それを崩すのがとても難しかったというところに、もしかしたらASDのこだわりの強さが影響していたのかもしれないな、と思っています。また、自己肯定感の低さも影響したのかもしれないな、なんて思ったりもしています。
山内先生:はい。発達障害と摂食障害を持っているという患者さんは比較的多く見られます。ただ当然、発達障害があっても摂食障害になっていない方々もたくさんいらっしゃいます。
ただし、合併している場合は症状が長引いたり、治療が思うように進まないという結果はあるかなと思います。
特にASDの方ではこだわりが強い方が多いですし、それで摂食障害の症状に嵌まってしまって抜け出すのに苦労するということもあります。それから、治療を受けられた後も、独特の理解をされたり、理解が難しかったりすることもあり、治療が思うように進まないということもあるのかなと思います。
――すんさんは、治療の中でご自身のこだわりに苦労されたことはありましたか?
すん:はい、ありました。カウンセラーさんに「こうしたら?」とか「こういう状況に陥っていると思うけれどどう思う?」とか言われても、反発したり、素直に受け入れられなかったりすることがありました。治療者からすれば一筋縄ではいかないと思われていたかもしれません。
発達障害の特性について自己理解を深めることは、摂食障害の症状の緩和に役立つ?
――発達障害の特性を自己理解していくトレーニングが、摂食障害の症状緩和に役立つのでしょうか?
すん:はい、2つあります。まず1つ目ですが、摂食障害を発症する方は完璧主義が強いとよく言われるかなと思いますけれど、ASDの特性として完璧主義というか、100点じゃなきゃいけないと思ってしまうようなことがあるかなと思います。そういうところを、デイケアなどで「完璧主義」などのワードに触れることで、もしかしたら脱却しやすくなるのかなと思いました。
それから、私は30歳くらいになってから発達障害の可能性を指摘されたんですね。周囲とのずれというか、ちょっと違うと感じていたところに「発達障害」という名前がついて。もしもっと早くその名前がついていたら、何か違っていたのかな、というようなことも思いました。自分が他の人と何か違うと思うところが、発達障害に起因しているのかもしれない、と認知することで、気を付けることができたかもしれない、と思いました。
山内先生:すんさんは30歳になってから発達障害の可能性を指摘されたということですが、診察をしているだけだと、発達障害の有無は意外と分からないこともあるんです。けれど、心理検査をしたり過去の苦労を詳しく聞いていると、やっぱり発達障害があるんだということに気づかされることがあります。
そういう風によくよく聞けば、完全主義、白黒思考のようなものがあるという方もいらっしゃるので、そういう意味では、しっかり話をして、患者さんのことをよく理解できるようになることが大事だと思います。発達障害を診断することで、患者さんが今までの苦労、自分の至らなさと感じていたことが、発達障害の特性から来ているんだとわかることで自分自身を責めずに許すことに繋がり助けられたと感じる方もいると思います。
ただ、発達障害ということを意識しすぎてしまうと、自分自身は発達障害だからとレッテルを貼って何でもそのせいにしてしまうようなところももあります。
ですので、発達障害の特性がどこまで症状に影響しているかとか、生活に影響しているかとかいったことを、自分で判断するだけでなく、周りの人の意見も参考にして判断するようにすすめています。
――発達障害の診断を受けるためのテストについて、摂食障害とか二次障害を併発しているなど認知機能が下がっている時って、テストの結果も変わって来るんでしょうか。
山内先生:はい、拒食症の人など栄養障害があると、健康なときの本来の姿がわからないくらい奇妙な言動、行動というのがみられるので、そういう時にテストをすると、結果が実際と変わってきますね。
私は摂食障害が重度なときに行った結果であれば、自己理解が対処法に繋がるというように、プラスに働く人には積極的に診断・告知するようにしていますけれど、そうでなければあまりその時の結果にクローズアップしないようにも気を付けています。
摂食障害の真っ只中で発達障害と言われた方が、摂食障害を回復した後でも発達障害の特徴を残すのか、あるいは摂食障害の症状から一時的にそのように見えていただけなのか。両方あると思います。