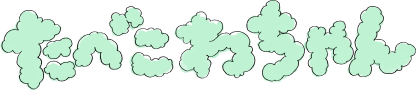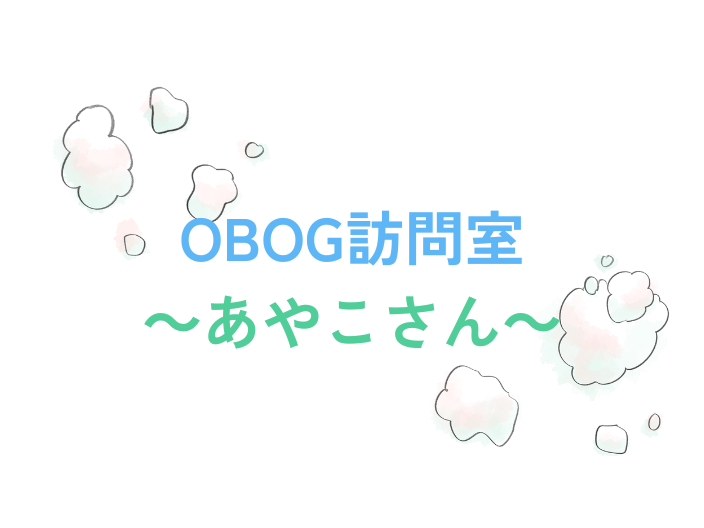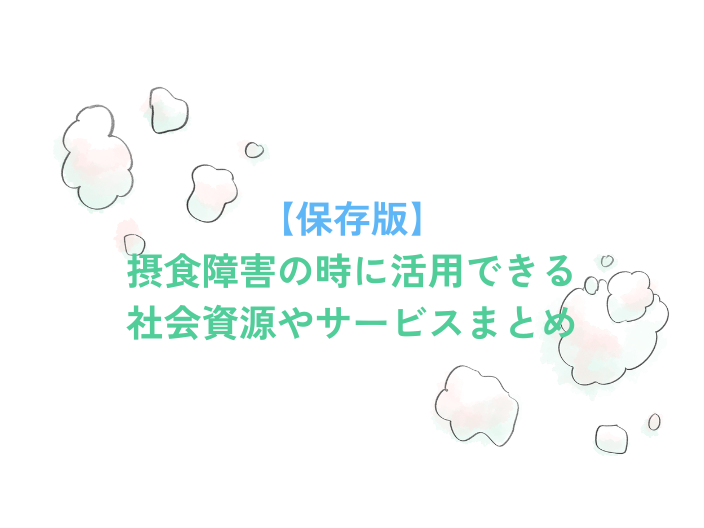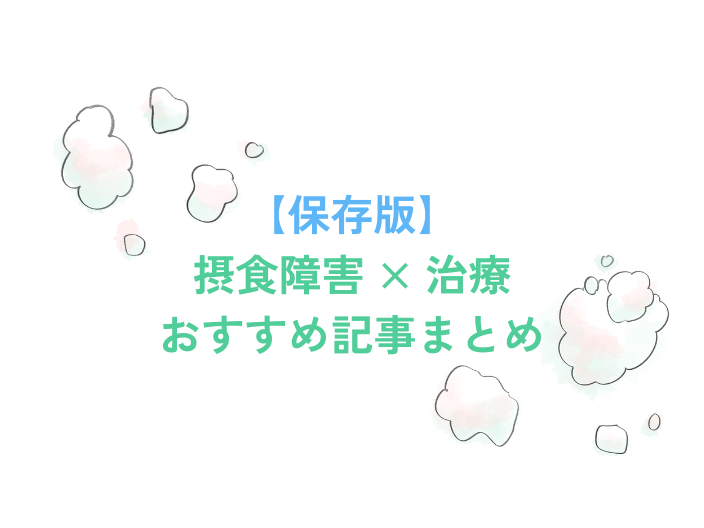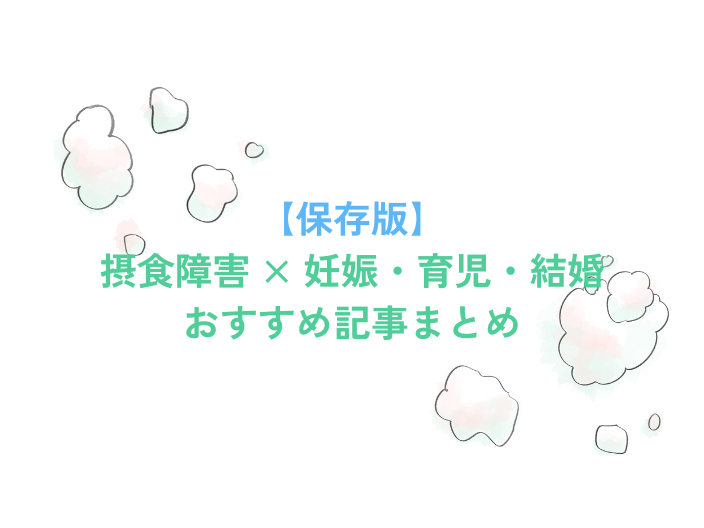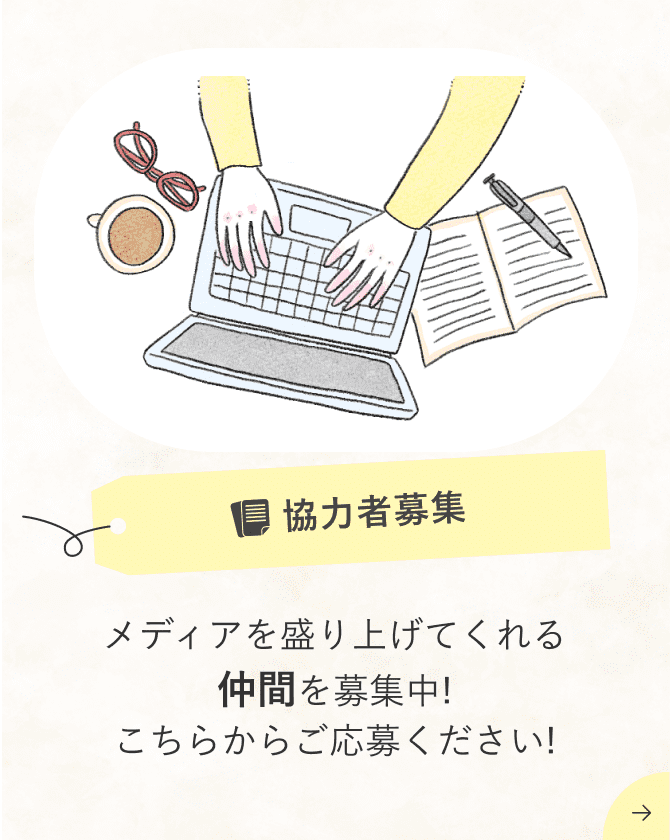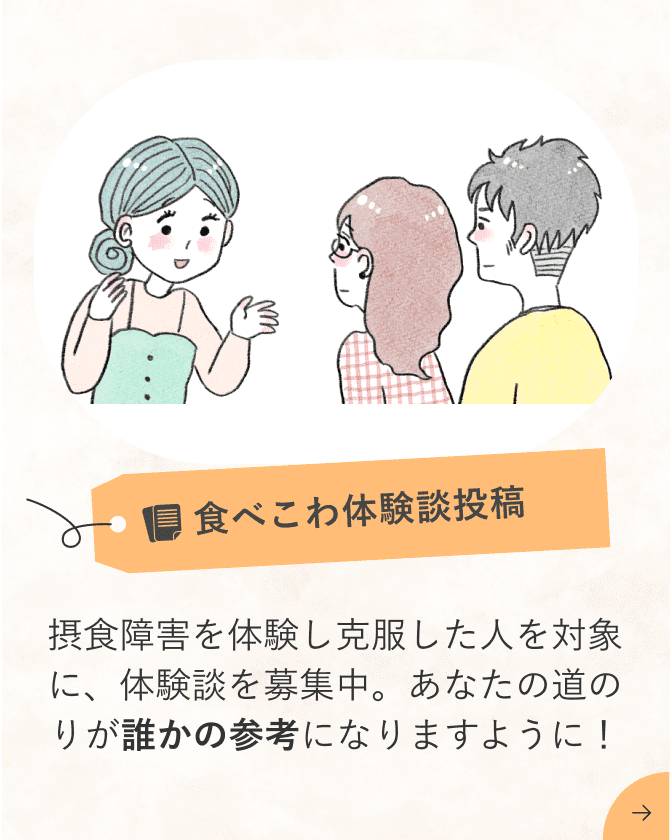「完璧にならなければ」というプレッシャー
── まず、摂食障害だった期間についてお聞きしても良いですか?
大学1年生の頃から4年間ぐらい摂食障害と向き合っていました。私の場合、「痩せたい」という気持ちが原因ではなく、自分のこころを後回しにしすぎてしまったことが大きかったと思います。
当時は「人は人、自分は自分」という考えがなくて、他の人の言うことを何でも聞いてしまう性格でした。「誰かのために何かしてあげたい」という気持ちが強くて、ついつい色々引き受けてしまって。
当時周りに深刻な悩みを抱えている人が多かったので、そんな環境も負担になっていたのかもしれません。自分の問題と他の人の問題の境界線がわからなくて、みんなの悩みまで自分が抱え込んでしまっていました。
それに加えて、ずっと完璧でなければいけないと思い込んでいたんです。「限られた世界でやっていくなら1番か2番にならないと社会ではやっていけない」と感じて。でも実際には、完璧とは真逆の性格なうえに実力も伴わず…自分を追い詰めていました。
── 完璧主義のような性格は、昔からだったんでしょうか?
昔からでしたね。家では品行方正であれ、ということをよく言われていました。私は当時は、人に何かを言われるのがすごく嫌だったんです。だから、何も言われないように、文句を言われないように、「完璧になればいいんだ」と思っていました。やり過ごすための戦略でもあったし、完璧であることで損はないから、期待に応えてもいいかなと思っていたんです。
症状への気づきと向き合った日々
── 摂食障害かもしれないと気づく、きっかけとなった出来事があれば教えてください。
気づいたというか、食事量を極端に減らしたりしていたので、自分でもなんとなくずっと実感はありました。なので、摂食障害だろうなというのは分かっていたんですけど、どうすることもできないまま、どんどん体重が減っていきました。カロリーの低いカップ麺やパン、 海藻ばかりを食べていたので、体に力が入らないし気力も湧かない。そういう違いを体で感じていました。
そして、歩くのもしんどいぐらいの状態になって初めて、病院に行ったんです。その時に「脳が萎縮している。このままだと危険だ」と言われました。当時、自分の中でも底についたような感覚があったのもあって、医者にこれを言われた時に、「もう一度ゼロからやり直そう」と思ったんです。何かを変える時には環境をガラッと変えなきゃいけないと感じて、大学もやめて、方向性も変えて、交友関係も全部変えました。
── 当時はどのように過ごされていましたか?
はじめはインド料理屋でバイトをしました。でもある日、「見た目が痩せすぎていて心配になるから、もう来ないで」って言われて首になってしまって。接客をする仕事だからというのは分からなくはないけれど、辛かったです。その後も何個かバイト面接を受けましたが、「働けなさそうだから」という理由で全部落ちました。
何の病気もない人って、世の中にそんなにいない気がするんです。多くの人が何かを抱えて生きているわけで。見た目だけで「この人は病気だ」と判断して拒否するのではなく、ちゃんと一人の人として接して欲しかったなと思います。 その後の1年間は、「自分の使命って何だろう」ってずっと考えていました。それまで人の期待に応えて生きてきたから、これからは自分のやりたいことや自分の使命を全うして死んでいこうと思いました。
料理との出会いが変えてくれたもの
── その後の生き方に影響を与えた、転機となる出来事はありますか?
バイトを辞めてから、「使命」を探すために習い事やイベントに参加して色々な世界を見てみたんです。その中で「食」にピンときたのと、摂食障害の時に一番食べるハードルが低かったたのがベジタリアン料理だったことがきっかけで、精進料理の先生のところに通うようになりました。 ベジタリアンの料理は、私にとって食べることへの恐怖心が比較的少なくて済むものだったんです。そういうところから少しずつ食事に慣れていけたのが後々の回復にもつながったのかもしれません。
通っていた精進料理の先生は、野菜だけを使っているのに全く物足りなさを感じさせない、本当に美味しい料理を作る方だったんです。野菜だけでこんなに美味しくできるなら、他の食材も使ったらもっと素晴らしい料理になるんじゃないかって思って。それが料理の専門学校に進もうと決めたきっかけでした。
摂食障害の時って、一食何かを食べた時の影響が大きいんですよね。何かを食べるのが怖いからこそ、一食を食べられたっていうのが成功体験になったりとか。普通に食べる人よりも、一食一食が貴重だからこそ感じていることだと思います。 そんな中で、食べ物って体を作るのはもちろん、誰かをポジティブな気持ちにしたりエンパワーメントできたりするんだなと実感したんです。その実感が、「人の役に立ちたい」「貢献したい」という気持ちと重なって、食でなにかできるかもと思いました。
── 専門学校での生活はいかがでしたか?
料理や食について「学ぶこと」自体は楽しかったんですが、実習での「試食」はやっぱりしんどかったです。フランス料理の学校だったのでバターもたっぷり使うし、午前も午後も調理実習があって。座学の授業でも試食が回ってくるし、どうしようって思っていました。 でも、容姿が理由でバイトをクビになった経験があったので、同じような理由で周りから拒否されるのが怖くて、自分が摂食障害だというのは一生懸命隠していました。
細いだけみたいに見せようとして、体型が見えない服を着たりもしていましたね。 食べられないものは「アレルギーが出たことがあって」とか「朝ごはん、いっぱい食べちゃったんだ」と言って他の人に手伝ってもらったりしていました。あまりに試食する頻度が高かったので、お腹いっぱいという理由もある程度通用したのかもしれません。
友人との出会いがきっかけで、食事を楽しめるように
── 回復につながった出来事などはありますか?
ある時、たまたまイタリア人の友達が沢山できたんです。イタリア人の人たちって本当に愛があるんですよ。それに、人の外見についてとやかく言う人が一人もいなかったし、食べたいか食べたくないかとかは自分で決めればいいと皆思っていたんです。
それがすごく心地よくて、よく一緒に遊んでいました。摂食障害とか「痩せている」とかっていうラベルを通してではなく、内面を見て、一人の人として接してくれたのがすごくありがたかったです。 友達に料理を振る舞ったりもしていたんですが、みんなすごく美味しいって言って食べてくれて。そういうところで、徐々に食が楽しいものに変わっていきました。
── 食べることへの恐怖はどのように克服されていったんでしょうか?
最初のうちは、誰かとご飯を食べること自体は楽しくなくていいと思うんです。
でも食事をする空間だったり、食べている空気感だったり、その場が楽しいと感じられる経験が大事だなって感じます。
摂食障害だというと、どうしても食べているか食べていないかばかりにフォーカスされがちだったんですが、それがしんどいし、プレッシャーなんですよね。だからこそ、食事の時間や空間を共有できる楽しさや幸せを、まず味わえることが大切だと思います。
同じ痛みを抱える人たちへ
── 同じような経験をしている人や周囲の人に伝えたいことはありますか?
周りに当事者がいる方には、まずは相手の気持ちを聞いてあげてほしいと思います。
当時、「痩せているから心配だよ」と言ってくる人が多かったんですが、私はその言葉をプレッシャーに感じてしまって。体型のことで特別扱いされたり、心配されすぎたりするのが辛い時期がありました。心配してくれる気持ちはありがたいのですが、一人の人として普通に接してもらえることが何より嬉しかったです。
当事者の方は変化していく見た目について悩んでしまうこともあると思うんですが、どんな状態であっても、その人らしさや美しさは変わらないということを伝えたいです。辛いことを言われることもあるかもしれませんが、それでも自分を大切にしてほしい。生きているだけで本当にすごいことだと思います。