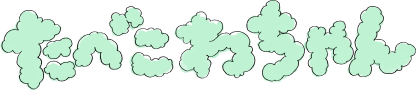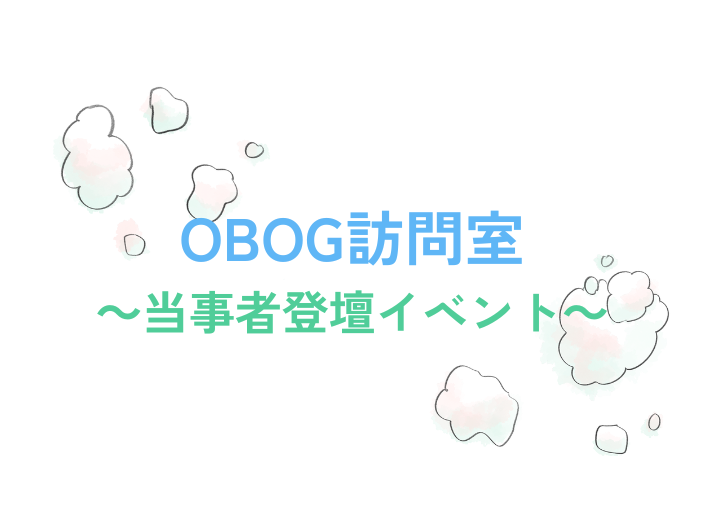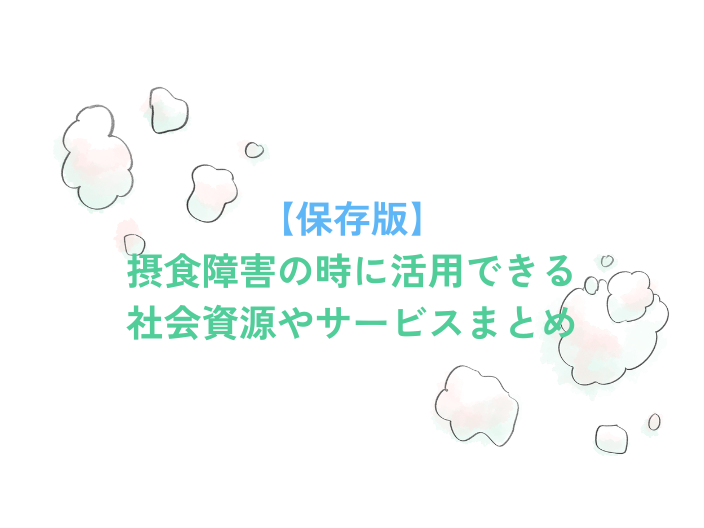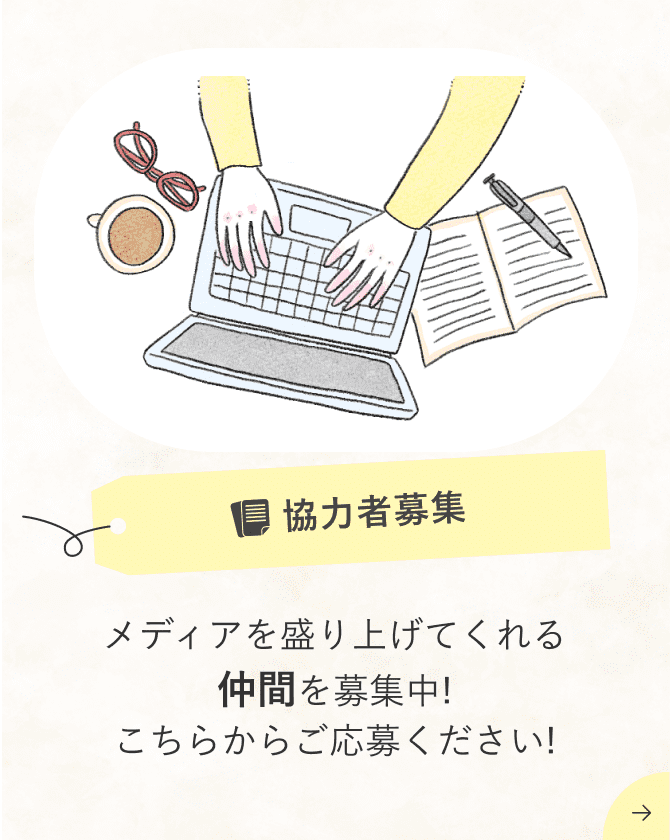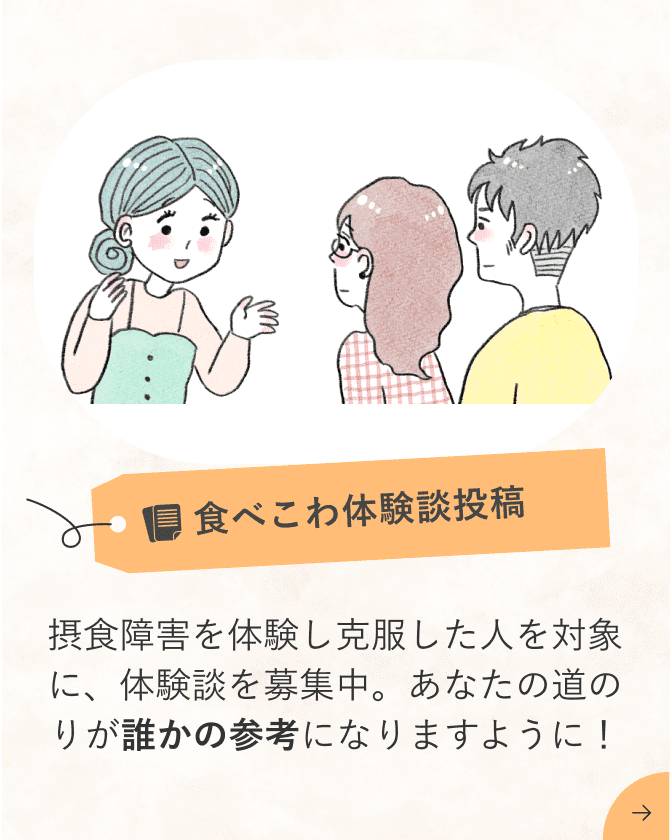完璧でなければ認められなかった子ども時代
── まず、摂食障害が始まったきっかけについて教えてください。
一番最初に自分の体重を気にかけるようになったのは、小学校2年生の時に、意識せず体重が減った時でした。2年生頃からの家庭環境の変化が影響していたと思います。環境の変化に伴い、1年生の頃はそうでもなかったのですが、母の勉学に対する姿勢が厳しくなりました。悲しさや悔しさの中、時には泣いたり反発しながらも、最終的には母の指示に従い、一度書いたものを最初からやり直したり、できるようになるまで繰り返しをするなど、辛かったことを覚えています。
でも、体重が減ったときは親がすごく心配してくれたんです。育ち盛りの子どもの体重が減るということはあまりないことなので。そのとき、体重が減ったり増えなかったり、病気になったり、何か異変があれば親が気にかけてくれると感じたのかもしれないですね。それ以降、体重を気にするようになったと思います。
── その頃のお母様との関係はどのようなものでしたか?
母には完璧主義的で、意識はしてないと思うのですが、時に皮肉的な一面がありました。また、父は仕事が忙しく、私が小学生になるまでは1、2年ごとに転居していたんです。なので、母は結婚してから、頼れる人が身近にいない中、ほぼ一人で3人の子どもの面倒をみていました。母なりに、私たちがちゃんと自立できるように育てたいという思いがあったんだと思います。私の可能性を最大限に引き出したいという親心から、教育への関心が強く、厳しい面がありました。
2年生以降、テストでいつも100点をとることが私にとっては当たり前だったんですが、ある時、音楽で96点をとったことがありました。自分でもちょっとショックだったのですが、母からも「音楽はダメなんだね」と言われてしまいました。通っていた塾で、成績が県内で上位10位以内に入ったことがあったのですが、それでも「こんな田舎で上位になっても、都会では大したことはない」と言われたのを覚えています。今振り返ると一緒に残念がったり、喜んでくれたらよかったのになと思いますが、当時は言葉をそのまま受け取ってしまい、「これじゃまだ自分はダメなんだ、もっと頑張らないといけないんだと」いう気持ちを抱いていました。
── 特に印象に残っているエピソードはありますか?
小学4年生の夏休みに、受験塾の講習で初めて受験算数に触れたのですが、予習では、それまでに出会ったことがない問題で最初はかなり苦戦しました。講習初日の帰り道、母に「天狗の鼻もこれで折れたね」と言われたのが心に残っています。それでも必死に取り組んで、最後のテストでは1番を取ったんです。でも、一緒に喜んでもらった記憶があまりありません。「初めてなんだから難しいよね。」「でもおもしろかったでしょ?」そんな言葉が本当は欲しかったのかなって思います。
── そんな中で、体調にも変化が現れてきたのですね。
頑張ってもどこか否定されてしまい、共感してもらえない寂しさと、いつも完璧でいなければいけないプレッシャーで、だんだん食べる量が減り、身長が伸びにくくなり、体重が減り始めました。走るスピードが落ちたり、運動能力も低下していったんですが、自分では「何でだろう」と疑問に思っている程度でした。
4年生の後半になると、給食もほとんど食べられなくなって、「体調が悪い」と言って迎えに来てもらったり、学校を休むことも増えていきました。「行きなさい」と言われた日は、一人で泣きながら学校に向かっていました。そんな中、5年生の春に両親から「学校に行かなくてもいいよ」と言ってもらえたときの安堵感は、今でもはっきりと覚えています。
6畳の個室で母と過ごした入院生活
── その後、入院されることになったのですね。
小学5年生での入院は私にとって、回復とそれに伴う葛藤や苦しみの始まりだったと思います。
学校を休むようになってからもほとんど食事をとることができませんでした。階段を登るのが困難になり、内臓機能など身体全体の調子も悪くなったため、入院することになりました。入院に対する反発もありほとんど食事を取らずにいたら意識を失ったため、点滴で強制的に栄養を入れる状態になってしまいました。それでも当時の私は点滴も外して欲しいと思っていました。意識してはいなかったですが、食べないことで静かに死にたいと思っていたのかもしれません。
でも、そんな中出会った管理栄養士さんが、すごく親身になってくれたんです。基礎代謝について教えてもらい、「何もしなくても、体を動かさなくても、これだけは食べても大丈夫なんだよ」と教えてくれたときは、少し安心できました。
── 具体的にはどのようなサポートを受けられたのですか?
私が安心して食べられるよう、色々と工夫してくれました。普通の牛乳ではなくスキムミルクにしてくれたり、砂糖の代わりに低カロリーの甘味料を使ってくれたり…。「十分に食べられなくても、ビタミンやミネラルだけはとっておこうね」と、比較的カロリーが低くて飲みやすい栄養補助飲料も紹介してくれました。色々試しながら、少しずつ食べられるようになっていったんです。
── 入院中、お母様との関係はいかがでしたか?
6畳くらいの個室で母と二人きりで過ごすのは、お互いにとって辛い時間でした。私は太るのが怖くて、じっとしていられず動き回っていたんです。そんな私をずっと見ていなければいけない母も、きっと大変だったと思います。でも、「あなたのせいで私の体調が悪くなる」と言われたときは、わかってもらえない悲しさと、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
フリースクールが開いてくれた扉
── 退院後の学校生活はどうでしたか?
退院後、学校には戻れず、その引け目でかつての友人関係も途切れていきました。友達は年相応に身体が成長していくのに、自分は痩せすぎで、成長も止まり、見た目は小学4年生頃のままというのも引け目でした。以前は一緒に遊んでいた友達と偶然会ったとき、何と言ったらいいのかお互いわからず、話すこともできなくなってしまいました。そんな中で出会ったのがフリースクールでした。週に2回、バスケットボールとバドミントンをやっていて、そこが私の新しい居場所になったんです。
(※ ご本人からのコメント:「成長については、他の人よりかなり長い時間がかかりましたが、体重が増えるのに合わせて身長も伸びました」)
── フリースクールでの経験はいかがでしたか?
バスケもバドミントンも最初は全然上手ではなかったんですが、少しずつ上達するのが楽しかったです。小さな進歩でも「すごいじゃん!」と喜んでもらえるのが嬉しかったのを覚えています。理由はそれぞれ違うけれど、学校に行けなくなったという共通点を持つ同年代の子たちとの繋がりもできて、通信制高校という選択肢があることも知りました。
初めて出会えた「同じ経験をした人」
── 大学進学も大きな転機だったのですね。
大学進学をきっかけに東京で一人暮らしを始めたのは、私にとって大きな転機になりました。食事を自分でコントロールできるようになって、無理やり食べなくてもいいし、余分な食べ物を家に置かなくてもいい。自分のペースで過ごせる環境になって、少し楽になったんです。
そして入学してすぐの4月、4年生の先輩との出会いも大きかったです。。その先輩に「さゆりって摂食障害でしょ?私も摂食障害なんだ」と言われたんです。その時に初めて、「自分だけじゃないんだ」と感じることができました。症状はそれぞれ違っても、所々で共感し合える関係が持てたことは、とても大きな救いでした。
自分らしくいられる環境との出会い
── 就職後の環境はいかがでしたか?
就職は、新たな発見の連続でした。ちょっとしたことでも「すごいね」「ありがとう」と言ってもらえたんです。最初は戸惑いもあったんですが、徐々に自分が役に立っているんだと実感できるようになっていきました。就職先の会社では過度な競争もなく、評価ばかりを気にしなくてもよかったんです。自分らしくいても大丈夫だと感じられてから、少しずつ自分自身のことも受け入れられるようになっていったと思います。
── その後、マラソンを始められたそうですね。
そうなんです。マラソンを始めたことで、食事への不安が和らぎました。時々食べすぎてしまうことがあったのですが、「走れば大丈夫」と思えるようになったんです。それから、食べすぎてしまった時の罪悪感や恐怖感、普段の食事のストレスも徐々に減って、食べすぎてしまうこと自体も自然と少なくなっていきました。
── ご結婚後の変化についても聞かせてください。
夫は私のことをそのまま受け入れてくれているように感じています。「そんなのじゃダメ」というような否定や押し付けがないので、安心していられます。
食事の面でも、夫の関わり方が私の回復を後押ししてくれました。摂食障害のことを必要以上に心配したり調べたりせず、外食するときは「どこで食べたい?」と私に選ばせてくれます。食べたくないときには無理強いすることもなく、食べてみたいけど全部は無理というときには、一口だけくれたり、半分こしてくれたりするんです。「どんな味なのか試してみたい」という気持ちを我慢しなくてもいいから、反動で食べすぎてしまうことも減りました。
私が摂食障害があることを夫に打ち明けたのは結婚後でした。でも、打ち明ける前も打ち明けた後も、接し方が変わるわけでなく、なんとなく理解してくれているのが私にとっては心地よいです。
自分が心地よくいられる「普通」の形
── 現在の食事や体調管理についてはいかがですか?
現在も、日常生活には摂食障害の影響が残っています。毎日体重を測り、だいたいのカロリー計算をし、食事パターンが決まっています。肉の脂身は取り除くなど、食べられないものもあります。あと、何かしら運動しないといけないという気持ちもあります。でも、これは慣れてしまって自然にやっていることなので、苦しいというより、自分が安心して食べることができるようにするるためのものなんです。これが今の私にとっての「普通」で、精神的にも身体的にも苦しむことは減りました。
── 最近の変化はありますか?
この3年くらい、ジムでトレーニングするようになってから安心して食べることができる量が増えました。食事の制限も前よりゆるやかになってきています。
ただ、社会生活の中では、みんなに合わせるべきか、自分の安心を優先するかで悩むこともあります。例えば、会社のランチ会でみんなが日替わり弁当を注文するとき。他の人に合わせた方がいいのかもしれないけど、メニューがわからないと「食べられないものが入っていたらどうしよう」と不安になってしまうんです。だから自分だけお弁当を持参しています。でも、それを受け入れてくれる環境があることには、本当に恵まれていると思います。
同じ痛みを抱える人たちへ
── 現在はピアサポーターとしても活動されているんですね。
はい、そうなんです。昔の私は「他の人に話して何になるの」と思っていました。でも実際に同じ経験をした人と話してみると、一人で抱えていたときとは全然違う感覚があるんです。「あ、私だけじゃないんだ」「こんな風に感じるのって普通なんだ」と思えるようになりました。
—— 同じように悩んでいる人に向けて、伝えたいことはありますか?
摂食障害を無理に治そうとする必要はないと思っています。私の場合、大学入学、就職、結婚と、環境が変わるごとに少しずつ良くなってきました。チャレンジしてみたけどうまくいかなかった時は戻ればいい。小さな一歩でも、勇気を出してチャレンジしてほしいです。
子どもの頃は、家族のルールが絶対的なものに思えました。でも外の世界に出ると、実はそうでないことも多いんです。自分では大したことないと思っていたことが、素晴らしい才能だったり、気にしていたことが、実はそんなに気にすることではなかったり。新しい環境で、そういう発見がたくさんありました。
同じ経験をした人と話をしてみることで、新しい扉が開くかもしれません。だから、できればあまり一人で抱え込まないでほしいです。完璧な回復を目指すのではなく、その時々の自分に合った付き合い方を見つけていく。それが、私が見つけた「自分らしい」回復の形だと思います。あなたも、あなたらしい回復の形を見つけてほしい。そう心から願っています。
さゆりさんとお話してみたい方へ
さゆりさんは摂食障害ピアサポート Ally Meの登録ピアサポーターとしても活動中です。
お話してみたい方は、下記リンクよりAlly Meについてご確認の上、お申し込みください。